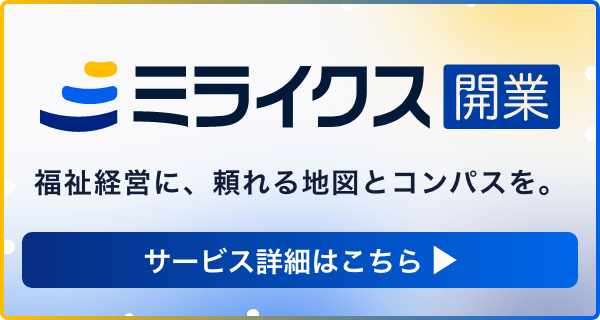事業を探す
2023.1.19
2023.3.20
放課後等デイサービスとは?事前に知っておきたい基礎知識

そのため、放課後児童クラブ(学童保育、学童クラブ)が利用できない子どもでも利用できます。
利用料には国の補助があり、世帯年収に応じて一定以上の金額にならない仕組みになっています。
そのため、家計に大きな負担をかけることもありません。
この記事では、放課後等デイサービスがどのようなものか、どのような子どもが通えるのか、どのような活動をするのか、そして料金体系や利用までの流れについて解説します。
目次
放課後等デイサービスの概要
放課後等デイサービスは、小学校から高校に通う子どもが放課後や土日、また長期休み時に利用できる福祉サービスです。
厚生労働省による「放課後等デイサービスガイドライン」では、放課後等デイサービスを以下のように説明しています。
放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づき、学校(幼稚園及び大学を除く。以下同じ。)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされている。
かみくだきつつ補足すると、次のようなことが言えます。
放課後等デイサービスは、発達障害などを含む障害のある子どもたちの居場所で、1度に10人程度の子どもたちが一緒に過ごす場所です。
子どもたちは個別の目標に合わせて支援を受けながら、施設のスタッフや友達と共に家ではできない集団生活を体験します。
放課後等デイサービスが生まれた背景は?
放課後等デイサービスは、2012(平成24)年に新しくできたサービスです。
以前は未就学児と就学児の両方が同じ施設に通っていましたが、2012年4月に児童福祉法が改正されたことにより、以下の2つに分かれました。
- 児童発達支援……未就学児が通う施設
- 放課後等デイサービス……就学児が通う施設
それぞれの施設について、児童福祉法6条2の2では以下のように定義されています。
児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう
違うのは、通う子どもの年齢です。
そのため、未就学児のうちは、児童発達支援センターや障害児保育などを利用していた方も、小学校に上がると同時に放課後等デイサービスへ移行する必要が出てきました。
放課後等デイサービスの役割は?
厚生労働省のガイドラインでは、放課後等デイサービスの基本的な役割を以下のように定義しています。
- 子どもの最善の利益の保障
- 共生社会の実現に向けた後方支援
- 保護者支援
それぞれ見ていきましょう。
子どもの最善の利益の保障
子どもの最善の利益について、放課後等デイサービスのガイドラインでは、以下のようにまとめられています。
放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものである。
子どもの最善の利益とは「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」の基本原則のひとつで「子どもにとって最もよいこと」を示します。
「利益」は、子どもが安心して過ごせること、幸せを感じられることを指すという考え方もあります。
つまり、放課後等デイサービスには、子どもが保護者と離れていても安心して過ごせる場所で、一人ひとりに合った発達支援を行うことが求められているのです。
共生社会の実現に向けた後方支援
放課後等デイサービスは、障害があっても地域社会に一体感を持って参加できるようにサポートする役割も担うべきとされています。
具体的には、放課後児童クラブ等の連携や保育所等への訪問支援が期待されています。
保護者支援
放課後等デイサービスには、障害のある子どもを育てる保護者を支援する役割もあります。
ガイドラインには具体的な支援例として以下があげられています。
- 子育ての悩み等に対する相談
- 子どもの育ちを支える力をつける支援(ペアレント・トレーニングなど)
- 保護者が心身を休めるためケアの一時的な代行(レスパイトケア)
放課後等デイサービスの要件は?
放課後等デイサービスには、児童発達支援管理責任者を配置しなければなりません。
児童発達支援管理責任者とは、個別支援計画を作成する知識とスキルを持った療育のリーダーとなる人材です。
また、スタッフの半数以上が児童指導員か保育士の資格を持っていることも必要です。
どの放課後等デイサービスにも、きちんと専門家が配置されるルールになっています。
▼放課後等デイサービスの配置基準の例
| 職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 1人以上 | なし | 原則として当該事業所の業務に従事すること |
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | あり | 人以上は専任かつ常勤 |
| 児童指導員または保育士 | 障害児が10人までの施設は2名以上 | あり | 1人以上は常勤で、営業時間中は常に配置することが原則 ※障害福祉サービス経験者は、令和3年3月以前に指定を受けた事業所のみ、令和5年3月まで配置できる |
※重症心身障害児以外を通わせる、定員10名までの放課後等デイサービスの場合
また、重症心身障害児認定を受けた児童を受け入れる場合は、医療的ケアが必要な児童の有無にかかわらず、看護師の配置が必要です。
▼重症心身障害児を受け入れる場合に追加される職種
- 看護職員(1人以上)
- 嘱託医(1人以上)
- 機能訓練担当職員(1人 ※機能訓練をおこなう時間のみ)
上記のスタッフのうち、看護職員は営業時間中を通じて1人以上配置することになっています。
医療スタッフが必要なため、医療機関や訪問看護ステーションなどの関連施設が比較的多いようです。
放課後等デイサービスにはどんな子が通えるの?

放課後等デイサービスの対象となるのは、学校に通う障害児です。
放課後児童クラブとは違い、親が就労していることを前提条件とはしていません。
続けて、詳しく解説します。
放課後等デイサービスの対象者
児童福祉法に定められた放課後等デイサービスの対象者は、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に通う6~18歳までの障害児です。
ただし、引き続き放課後等デイサービスを受けなければ、その福祉を損なうおそれがあると認められた場合は、特例として20歳まで放課後等デイサービスを利用できます。
障害児の定義は以下のとおりで、障害者手帳や療育手帳などの有無は問われません。
(1)身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
(2)発達に特性があり、児童相談所・市町村保健センター・医師等により療育の必要性が認められた児童
そのため、医学的な診断名がついていない子どもも多く利用しています。
なお、重度心身型の放課後等デイサービスの対象となるのは、重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複する重症心身障害児です。
両親共働きでも放課後等デイサービスを利用できる?
両親共働きでも、放課後等デイサービスを利用することは可能です。
しかし、実際には注意すべき点もあります。
事業者によって利用時間が異なるため、終業時間が放課後等デイサービスの利用時間よりも遅くなる可能性があります。
車で送迎してくれる事業者もありますが、できれば送迎時間に保護者が自宅にいたほうがよいでしょう。
もし、どうしても時間の折り合いがつかないようならば、仕事か施設のどちらかを変える、祖父母に協力を頼むなどの対策も必要かもしれません。
夏休みや冬休みなどの長期休暇時に、日中から利用できる施設は多くあります。
ただし、長期休暇中は学校登校日と登所・降所時間が異なる場合があるので、注意が必要です。
延長利用ができる施設もあるので、事前に対応を考えておきましょう。
1ヶ月ごとの利用回数の上限は受給者証によって決まっていますが、回数の範囲内であれば複数施設を掛け持ちで利用することもできます。
学童クラブや日中一時支援などとの併用も、長期休みを乗り切る方法の一つです。
放課後等デイサービスではどんなことをするの?
学童保育のように自由時間が多い施設もあれば、学習や生活訓練のプログラムに特化した施設、また専門的な療育を行う施設まであり、サービス内容は事業者によってさまざまです。
しかし、どの施設であっても児童発達支援管理責任者が個別支援計画書を作成し、それを元に一人ひとりの特性に合わせたプログラムを行っています。
続いて、放課後等デイサービスでどんなことをするのか、具体的に紹介しましょう。
放課後等デイサービスのプログラム内容の例

ここでは、療育に力を入れている事業者を例にとり、放課後等デイサービスでどのようなことが行われているのかをお伝えします。
- 療育プログラム
社会の中で暮らしていくために必要なソーシャルスキルトレーニングをベースにしたプログラムを行う。
・工作、実験、料理
・ゲーム(記憶、音感、英語遊びなど)
・ダンスレッスン など
- 季節ごとのイベント
-
・農業体験
・みかん狩り など
例に挙げた施設では、子どもが社会生活を営むために必要なスキルを養う療育プログラムとして、上記のような活動を行っています。
子どもたちの五感を刺激し、楽しみながら指先を使う訓練をしたり、集中力を養ったりすることも重視しているそうです。
そのほか、宿題・学習の時間や自由時間、おやつの時間などもあります。
帰宅前の掃除や片付けも、療育の一環として子どもたち主導で行うなど、自立を促すことも大切にしています。
放課後等デイサービスに通うメリット・デメリット
放課後等デイサービスには、以下のメリットとデメリットがあります。
▼放課後等デイサービスのメリット・デメリット
- コミュニケーション能力や社会性の向上につながる
- 学習能力の向上につながる
- 学校・自宅以外に居場所ができる
- 保護者の負担が軽減される
- 事業者により特色が異なる
- 見学・体験しないと詳細はわからない
- 子どもの負担になる可能性がある
- 手続きや更新の手間がかかる
- 利用回数の上限が決まっている
放課後等デイサービスのメリット
放課後等デイサービスで、子どもは家族以外の大人や友達と共に過ごします。
子どもたちは、自分の思いどおりにいかないこともたくさん経験するでしょう。
集団生活の中でさまざまな葛藤と折り合いをつけることや友達と譲り合うことなどを学び、社会の一員として生きていくために必要な力が身に付きます。
「子どもが放課後等デイサービスに通うのが好きで積極的に行くため、家族で過ごす時間がなかなか取れなくなった」という声がしばしば聞かれるほど、放課後等デイサービスは子どもたちとって良い居場所となっているようです。
そのほか、計算や文章を書く訓練をする施設もあり、学習能力の向上につながるケースもあります。
保護者が就労していなくても利用できるので、自分の時間を作ってリフレッシュできるのもメリットといえるでしょう。
放課後等デイサービスのデメリット
放課後等デイサービスは、事業者によって療育の内容や質が変わってくるため、見学や体験は必須といってよいでしょう。
子どもに合わない施設だった場合、本人の負担となってしまう可能性もあります。
また、受給者証の申請・更新を年1回、それに必要な支援計画書の作成に向けた面談(アセスメント)などを6ヶ月に1回以上のペースで行わなければなりません。
また、月ごとに下校時刻などの利用予定を事業者に伝えるなど、細かい連絡・調整が必要です。
放課後等デイサービスの利用料金は何割負担?
放課後等デイサービスは、障害児給付費の対象となる福祉サービスです。
通所支援受給者証を取得すれば、1割の自己負担(残り9割は公費負担)でサービスを利用できます。
利用料金は自治体や事業所などにより異なりますが、1回につき1,000円程度が目安です。
ただし、世帯収入によって負担上限月額が決まっているため、その金額を超える負担をすることはありません。
▼月あたりの利用料の上限| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円※未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※収入がおおむね890万円以下の世帯が対象
放課後等デイサービスの利用の流れ
放課後等デイサービスを利用する際は、下記のようなステップが必要です。
- 自治体の福祉窓口に相談
- 施設の見学・体験
- 障害児通所給付費支給申請書提出~調査
- 通所受給者証の交付
- 事業者と契約
- サービスの利用開始
続いて、一つずつ詳しく解説します。
1. 自治体の福祉窓口に相談
まずは、自治体の障害福祉部や子育て相談窓口に電話をするか、直接訪問してみましょう。
その際に、以下の2点を伝えると話がスムーズになるはずです。
- 放課後等デイサービスの利用を希望していること
- 相談支援が提供されている自治体ならば、相談支援を利用したいこと
相談支援事業所があれば、担当者が放課後等デイサービス探しや申し込みをサポートしてくれます。
相談支援の利用が放課後等デイサービスの申し込みに必須となる場合もありますが、相談支援の利用料負担はありません。
翌年4月から利用したい意向があるならば、前年度の11〜12月までには窓口へ相談に行くことをおすすめします。
ちなみに、自治体の窓口やホームぺージでも、放課後等デイサービスや相談支援事業所のリスト、申請書類一式を入手できる場合があります。
自分でできることを進めていきたい方は、まず自治体のホームページをチェックしてみてください。
2. 施設の見学・体験
興味のある施設や通えそうな施設がいくつか見つかったら、見学や体験を申し込みましょう。
施設によって療育プログラムに違いがあるので、実際に見学・体験して比較検討するのがおすすめです。
たとえば、生活能力向上に注力している施設、療育に特化している施設、習い事に近い内容を提供する施設などがあります。
実際に足を運び、スタッフの話を聞いたり、通っている子どもたちの様子を見たりすると、自分の子どもが通うイメージもわきやすいでしょう。
スタッフとの相性も大切なので、現地に行ってみることが大切です。
3. 障害児通所給付費支給申請書提出〜調査
利用したい放課後等デイサービスが決まったら、必要書類を自治体に提出しましょう。
必要書類は自治体により異なる場合があるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
- 障害児通所給付費支給申請書
- マイナンバーを確認できる書類(申請者と利用者)
- 収入を示す書類(市民税非課税世帯証明書)
- 発達支援の必要性を証明する書類(障害者手帳や療育手帳、医師の診断書や意見書など)
- 障害児支援利用計画案(セルフプランも可)
相談支援を利用する場合、相談支援員が家庭を訪問するなどして聞き取りを行ったうえで利用計画案を作成し、自治体に提出する流れとなります。
相談支援を利用しない場合は、サービス提供事業者のサポートを受けながら保護者が作成する「セルフプラン」でもかまいません。
書類を提出したら、自治体が利用者本人やどのようなサービスを利用したいかなどについて聞き取り調査を行います。
4. 通所受給者証の交付
提出書類や聞き取り調査の内容に基づいて自治体による審査が行われます。
7~10日程度で支給決定される自治体もあるようですが、混雑なども考慮して1ヶ月ほど見込んでおくことをおすすめします。
支給が決定したら、支給決定通知と受給者証が交付されます。
受給者証を手にするまでに放課後等デイサービスの見学を進め、利用したい施設を決めておくとよいでしょう。
5. 事業者と契約
受給者証をもらったら、放課後等デイサービスとの契約ができます。
事前に見学などをして利用を決めた放課後等デイサービスに連絡をし、受給者証を受け取ったので契約をしたい旨を伝えましょう。
契約の際は、以下を行います。
- 利用契約書や重要事項説明書の確認
- アセスメント用紙や与薬および医療的処置依頼書の記入
- アセスメント用紙に基づく面談
契約が済むと、児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成します。
後日その内容を確認し、問題がなければサインをしてください。
6. サービスの利用開始
個別支援計画の承認によって手続きは終了となり、放課後等デイサービスを利用できるようになります。
なぜ今放課後等デイサービスが増えているのか?
放課後等デイサービスについて調べてみると、さまざまな事業者が開設していることに驚く方もいるでしょう。
実は、放課後等デイサービスは2012(平成24)年から2020(令和2)年にかけて事業所数が約5倍に増加しており、利用者数も4~5倍に増えています。
これは、利用者側の支援ニーズが高まっていることと、放課後等デイサービスが事業として魅力的であることが主な理由です。
放課後等デイサービスは、福祉事業であることから税制面が優遇されています。
つまり、利益率が安定しているので、ビジネスとして参入してくる事業者が多くいるのです。
しかし、ビジネスマインドで参入してくる事業所が増えてきたことで、施設による支援内容のばらつきが生じ、そのことが問題視されるようになりました。
単なる学習塾の延長になっているような施設やテレビアニメを見せているだけの施設の存在が、ニュースなどでも取り上げられるようになったのです。
そこで厚生労働省は、2021(令和3)年10月に放課後等デイサービスを「総合支援型」と「特定プログラム特化型」の2類型に分ける方針を打ち出しました。
これは、放課後等デイサービスで障害の特性に合わせた支援を行えるようにするための施策です。
一定水準以上の質を担保できない事業所は、今後、給付の対象外となる可能性があります。
ミライクスの放課後等デイサービス実践講座ならば、研修型コンサルティングを受けられるため、放課後等デイサービスを取り巻く環境の変化にも強い知識を身につけられます。
開業後のロイヤリティは、一切ありません。
放課後等デイサービスを開業したいと考えている方は、ぜひ一度、ミライクスの無料セミナーにお越しください。