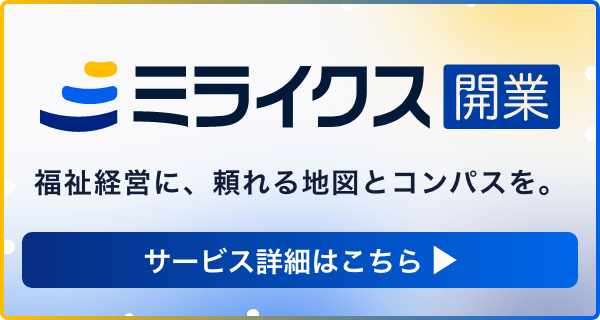事業を探す
2023.1.20
2023.1.18
生活介護とは?デイサービスとの違いから対象者・活動内容まで解説

また、生活介護は就労の機会を提供する役割も果たしています。
生活介護に携わるのは生活支援員やサービス管理責任者のほか、医師や看護師などの医療従事者です。
この記事では、生活介護の対象者や活動内容・支援内容、他の介護サービスとの違い、利用料、利用の流れまで詳しく解説します。
目次
生活介護とは?
生活介護は、平成25年4月1日に施行された障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつです。
生活介護のサービス提供者は、障害者支援施設や生活介護事業所です。
主に生活支援員が介護や日常生活上の支援、看護職員が健康管理を行います。
また、理学療法士や作業療法士によって機能訓練が行われる場合もあります。
生活介護はデイサービス(通所介護)や居宅介護と似ていますが、それぞれ対象者や目的、サービス内容などが異なる障害福祉サービスです。
生活介護とデイサービス(通所介護)の違い
生活介護とデイサービス(通所介護)では、対象者や目的が異なります。
デイサービス(通所介護)は要介護1〜5の認定を受けた人を対象に、利用者が自宅で自立した日常生活を送ることができるように支援する介護サービスです。
自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消、心身機能の維持、家族の介護負担を軽減することなどを主な目的としています。
一方、生活介護は常に介護が必要な障害者を対象に、日常生活の介護や支援、創作的活動・生産活動の機会の提供、身体機能や生活能力の向上を目的とするものです。
▼生活介護とデイサービス(通所介護)の違い
| サービス | 生活介護 | デイサービス(通所介護) |
|---|---|---|
| 対象 | 常に介護が必要な障害者 | 要介護1〜5の認定を受けた人 |
| 目的 | ・日常生活の介護や支援 ・創作的活動や生産活動の機会の提供 ・身体機能や生活能力の向上 | ・日常生活の自立 ・孤立感の解消 ・心身機能の維持 ・家族の介護負担軽減 |
| 根拠法 | 障害者総合支援法 | 介護保険法 |
生活介護と居宅介護の違い
生活介護と居宅介護は、どちらも障害福祉サービスという点は同じですが、サービス内容が異なります。
居宅介護は、身体介護(食事、排せつ、入浴、着替えなど)、家事援助(調理、掃除、洗濯、生活必需品の買いものなど)のほか、通院時の乗降や移乗の介助を行うサービスです。
これに対して生活介護では、身体介護や家事援助の内容はほとんど変わりませんが、創作的活動および生産活動の機会の提供や、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助が受けられる点が大きく異なります。
▼生活介護と居宅介護の違い
| 生活介護 | 居宅介護 | |||
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 障害支援区分3以上の人 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上 ※詳細は次項で解説 | 障害支援区分1以上の人 | ||
| サービス内容 | ・身体介護 ・家事援助 ・生活等に関する相談、助言 ・日常生活上の支援 ・創作的活動、生産活動の機会の提供 ・身体機能や生活能力の向上のために必要な援助 | ・身体介護 ・家事援助 ・通院等介助(※) ※障害支援区分2以上で歩行・移乗・移動・排尿・排便の支援が必要な方 | ||
| 根拠法 | 障害者総合支援法 | 障害者総合支援法 | ||
| 通常 | 施設入所支援を併用 | |
|---|---|---|
| 50歳未満 | 障害支援区分3以上 | 障害支援区分4以上 |
| 50歳以上 | 障害支援区分2以上 | 障害支援区分3以上 |
施設に入所している人で、もし上記の障害支援区分に満たなかったとしても、市区町村が利用の組み合わせを認めた場合には生活介護の対象となります。
例えば、50歳以上で障害者支援施設に入所している障害支援区分2の人の場合、市区町村に生活介護を利用する必要性が認められれば対象になるということです。
ただし、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成手続きをしておく必要があります。
65歳以上は原則として介護保険が優先される
65歳以上の人が障害福祉サービスの利用を希望しても、重複する介護保険サービスがある場合は、障害者総合支援法第7条の規定により原則として介護保険サービスが優先されます。
65歳の誕生日を迎える生活介護の利用者には、事前に自治体から介護保険利用の案内が届きます。
その際に介護保険の認定調査で要介護1〜5の認定を受けた人は、デイサービス(通所介護)などの介護保険サービスに切り替わる可能性があります。
ただし、一律に介護保険サービスを優先的に利用するわけではありません。
心身の状況やサービス利用の意向といった申請者の個別状況に応じて、必要な支援内容を介護保険サービスによって受けられるかどうか、市区町村において適切に判断するよう厚生労働省が通知しています。
以下に当てはまる場合は、65歳以上でも障害福祉サービスを利用できる可能性があります。
65歳以上でも障害福祉サービスを利用できるケースの例
- 市区町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみでは確保できない場合
- 介護保険サービスを提供する事業者や施設が近くにない場合
- 近隣の介護保険サービスの利用定員に空きがない場合
- 自立訓練や就労継続支援といった障害福祉サービス固有の支援が必要な場合
生活介護の利用者数の9割を区分4〜6の利用者が占める
令和2年4月における生活介護の利用者数は28万8,763人でした。
障害支援区分別に見ると、直近の3年間では区分5と区分6の利用者数が増えており、令和2年4月においては区分4〜6の利用者が利用者総数の90.7%を占めています。
特に区分6の利用者割合は42.9%と高くなっています。
| 総数 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年4月 | 281,521 | 58,805(20.9) | 76,953(27.3) | 117,637(41.8) |
| 平成31年4月 | 286,915 | 58,723(20.5) | 78,687(27.4) | 121,916(42.5) |
| 令和2年4月 | 288,763 | 58,524(20.3) | 79,477(27.5) | 123,924(42.9) |
※()内は総数に対する割合(%)
生活介護の具体的な支援内容は?

生活介護サービスを提供する障害者支援施設や生活介護事業所では、主に昼間に以下の支援を受けられます。
生活介護の支援内容
- 身体介護(食事や排泄、入浴の介助)
- 家事援助(調理や洗濯、掃除など日常生活の援助)
- 創作的活動または生産活動の機会の提供
- 生活などに関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の支援
- 身体機能または生活能力の向上のために必要な支援
このうち主な支援内容となる、身体介護、家事援助、創作的活動または生産活動の機会の提供について、さらに詳しく解説します。
身体介護
身体介護は利用者の身体に直接触れて行う介助サービスのことで、日常生活動作(ADL)・IADL(手段的日常生活動作)・QOL(生活の質)や生活意欲の向上を目的として行われます。
また、医療などの専門的知識・技術をもって行うサービスも身体介護の一部です。
具体的には以下に挙げる支援内容が該当します。
身体介護の支援内容
- 排泄・食事介助 清拭・入浴、身体整容
- 体位変換、移動・移乗介助、外出介助
- 起床・就寝介助
- 服薬介助
- 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
なお、夜間・休日の介護は障害福祉サービスの「施設入所支援」で受けられます。
生活介護と施設入所支援を併用することで、利用者が日常生活を不安なく送ることが可能です。
家事援助
家事援助では、主に調理や洗濯、掃除などの援助を行い、日常生活に支障がないようにサポートします。
家事にかかわる周辺的な援助も含むため、支援内容は広範です。
例えば調理においては、配膳や下膳、食器洗いなどの後片付けまで行います。
洗濯なら衣類干しと取り込み、アイロンがけなどです。
創作的活動または生産活動の機会の提供
創作的活動や生産活動を通して、利用者が知識や技術を学んだり、集団活動に必要な協調性・社会性を身につけたりすることができます。
創作的活動や生産活動の内容は施設によってさまざまです。
利用者が地域とのつながりを持てるように、イベントの開催や近隣の学校との交流を定期的に行っているケースもあります。
創作的活動または生産活動の例
- 散歩
- ドライブ
- レクリエーション
- 清掃活動
- 手芸
- 陶芸
- 園芸
- 絵画
- 音楽鑑賞
- 演奏・合唱
生活介護に工賃の支給義務はある?
生活介護の利用者が生産活動を行った場合、障害者支援施設や生活介護事業所には工賃の支払い義務が発生します。
生活介護における工賃とは、生産活動を通じて収益が発生した場合に、利用者が得られる報酬のことです。
生産活動で得られた事業収入から事業経費を差し引いた額が支払われます。
一般的な労働契約に基づく賃金とは異なりますが、仕事への対価としての意味合いは似ています。
工賃の支払いは利用者の意欲向上につながり、自立生活支援の観点から見ても重要なものといえるでしょう。
ただし、工賃の支払金額は事業者側で自由に決定でき、下限額の規定や報告義務もありません。
一方で、以下のような制限があります。
- 生活介護の生産活動は、主として昼間に行うという時間的制約がある
- 生活介護の就労では、業務量が追いつかなくても残業等がない
- 生活介護における就労機会の提供は、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定められる施設のみで認められる
それでは、もう少し詳しく工賃について解説します。
生活介護の工賃の平均金額
日本知的障害者福祉協会「令和2年度 生活介護事業所(通所型)実態調査報告」によると、工賃を支給している事業所の平均工賃月額は3,000円未満の事業所が最も多く45.6%でした。
次いで3,000円以上5,000円未満が19.7%、5,000円以上1万円未満が17.3%で、1万円以上を支給する事業所の割合は11.2%となっています。
また、独立行政法人福祉医療機構(WAM)「2020 年度(令和2年度)日中活動系障害福祉サービスの経営状況」では、2,607の事業所における利用者1人1月当たり平均工賃が3,974円であると報告されています。
生活介護と就労継続支援B型事業所の違い
生産活動に対する工賃は「就労継続支援B型」でも支払われます。
就労継続支援B型とは、障害や難病のある人で、年齢や体力などの理由から雇用契約を結んで働くことが困難な場合に、比較的簡単な作業の就労訓練が行える福祉サービスです。
生活介護と就労継続支援B型は、事業所と雇用契約を結ばずに就労機会の提供が受けられる点では同じですが、作業時間と工賃に関しては以下の違いがあります。
▼生活介護と就労継続支援B型の違い
| 生活介護 | 就労継続支援B型 | |
|---|---|---|
| 作業時間 | ・日中のみ ・早番・残業は認められない |
・時間帯の制約はない ・早番・残業も可能 |
| 工賃 | ・下限額の設定はない ・報告義務はない |
・月額平均が3,000円以上 ・都道府県への報告が必要 |
就労継続支援B型は就労支援が目的であるため、より一般的な職場に近い働き方ができます。
その一方で、生活介護の生産活動の提供は、利用者の就労ではなく知識や技術の習得、あるいは集団活動を通じた社会性や協調性の向上がねらいです。
両者の制度趣旨の違いが、作業時間と工賃に関するルールの違いに現れているといえます。
市町村に必要性が認められれば、生活介護と就労継続支援B型の併用も可能です。
原則として報酬単価が日額で算定される障害福祉サービスを同じ日に利用することはできませんが、日中活動サービスと宿泊型自立訓練の両方が必要と認められた場合に併用できます。
ただし、複数サービスの支給決定が必要であることの理由書や、併給を希望する理由が明記されたサービス等利用計画の提出が必要です。
生活介護事業所での1日の過ごし方
生活介護の利用を検討している人の中には、1日のスケジュールがどのようになるのか気になる人もいるでしょう。
ここでは、生活介護を受ける場合に、サービスを提供する事業所で1日をどう過ごすのか紹介します。
▼生活介護事業所の1日の流れの例(イメージ)
| 9:00〜9:30 | 登所・朝の会 | |
|---|---|---|
| 9:30〜10:30 | バイタルチェック、作業等準備など | |
| 10:30〜11:30 | 午前の活動 | |
| 11:30〜12:00 | 昼食準備 | |
| 12:00〜13:00 | 昼食・休憩 | |
| 13:00〜13:30 | 歯みがき、作業等準備など | |
| 13:30〜14:30 | 午後の活動 | |
| 15:00 | 帰りの会・降所 | |
朝の8時30分〜9時30分頃に専用車で送迎され、事業所に到着します。
登所後に体温や血圧、脈拍をはかるバイタルチェックを受け、入浴や午前の活動の準備を行います。
通常は午前と午後に活動時間を設定し、活動内容は施設・事業所ごとにさまざまです。
体操やレクリエーションなどの体を動かす活動や、創作的活動または生産活動を行います。
事業所が用意する昼食をとって休憩した後、歯みがきを済ませて午後の活動を開始します。
生活介護が終わる時間は各施設・事業所の規定や利用者の希望によって変わりますが、だいたい15時~16時です。
降所時には専用車で自宅まで送ってもらいます。
生活介護の利用料は?
生活介護には利用料のほか、食費などの実費がかかります。
利用料の1割を利用者が負担しますが、残りの9割は国や都道府県、市区町村が負担する仕組みです。
月ごとの利用者負担額は、前年の世帯収入によって上限額が定められていて、生活保護受給世帯または低所得世帯であれば無料で生活介護が受けられます。
▼月ごとの利用者負担額の上限
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
|---|---|
| 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※2) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(※3) |
9,300円 |
| 上記以外の世帯 | 37,200円 |
※1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
※2 収入が約600万円以下の世帯が対象
※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「上記以外の世帯」となる
施設に入所している利用者の場合は、食費などの実費負担においても以下の条件で減免措置が受けられます。
20歳以上の入所者の場合
入所施設の食費・光熱水費の実費負担の限度額は53,500円です。
ただし、低所得者に対する給付については費用の基準額を53,500円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、25,000円以上が手元に残るよう補足給付がなされます。
通所施設の場合
市町村民税非課税世帯や市町村民税課税世帯の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額の3分の1程度になります。
生活介護を利用するには?
生活介護は障害福祉サービスのうち介護給付にあたります。
したがって、以下の流れに沿った障害福祉サービスの利用手続きを行うことになります。
1.相談・申請を行う
市区町村の障害福祉担当窓口、あるいは相談支援事業者に相談してアドバイスをもらいます。
事前にどのような支援が必要になるか、どの程度のサービスを希望するのかを利用者自身も確認するためです。
生活介護を利用することが決まったら、障害福祉担当窓口へ申請します。
申請には以下の書類等が必要です。
生活介護の必要書類
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)
- 住民税額調査の同意書または住民税額の証明書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの障害者手帳
2.障害支援区分認定を受ける
認定調査では、市区町村の認定調査員との面接を行います。
面接は申請者の心身の状況と概況を調査するのが目的です。
同時に、市区町村は申請者のかかりつけ医に対し、医師意見書を依頼します。
認定調査と医師意見書の結果に基づいて、コンピュータによる1次判定が行われます。
1次判定の結果と概況調査、医師意見書などを踏まえて市区町村審査会で2次判定がなされ、区分1から区分6、または非該当の認定が行われるという流れです。
3.サービス等利用計画案の提出
サービス等利用計画案を、申請者自身または特定相談支援事業者が作成し、市区町村へ提出します。
特定相談支援事業者が作成する場合には、申請者が生活を送るうえで必要な支援、あるいは申請者と家族が希望する支援などの聞き取りを行います。
4.サービス等の利用の支給決定
生活介護の支給が決まる重要なフェーズです。
ここでは、市区町村が障害者認定区分や提出されたサービス等利用計画案、家族構成、申請者や家族の状況および意向、その他の勘案すべき事項を踏まえ、支給について検討します。
サービスの支給量を決定した後、申請者への通知と受給者証の交付を行います。
受給者証の記載事項は、障害支援区分や支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担上限月額などです。
5.サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、申請者自身または指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成します。
指定特定相談支援事業所が作成した場合は、サービス提供事業者間の調整やサービス受給後の定期的なモニタリングを行ってもらうことができます。
6.サービス等の利用開始
申請者とサービス提供事業所との間で契約を結べば、いよいよサービスの利用開始です。
サービス開始後も、一定期間ごとに支給量や内容などの確認・見直しが行われます。
申請から利用開始までの期間は申請の時期や市区町村の対応によって異なります。
長ければ2~3ヶ月程度かかるケースもあるため、利用を希望する場合にはできるだけ早く申請しておくとよいでしょう。
障害福祉事業を始めたい方へ

日本の障害者人口は増加傾向にありますが、障害福祉サービスはまだ十分には行き届いていません。
ミライクス開業支援では、放課後等デイサービス・就労継続支援B型・グループホーム(共同生活援助)の開業を目指す方の支援を行っています。
約半年間の実践的な研修を通して、開業後の経営も見据えた準備をサポートいたします。
ご興味のある方は、以下の資料をぜひご覧ください。