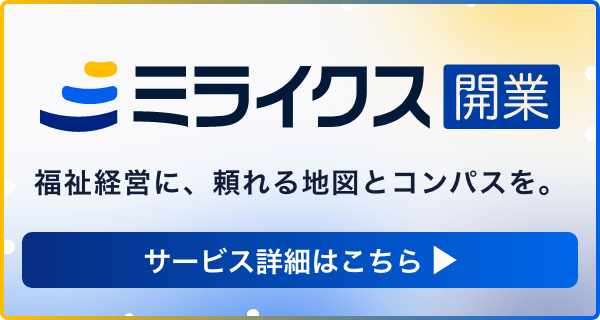事業を探す
2023.8.23
2023.7.12
就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違いは?対象者から賃金まで徹底比較

就労移行支援と就労継続支援はどちらも障害のある方を対象とした就労系障害福祉サービスです。
それぞれの制度目的には違いがあり、就労移行支援は就職するために必要なスキルを身につけること、就労継続支援は就労・生産活動の機会を提供することを目指しています。
対象者や雇用契約などにも相違点があることに注意が必要です。
この記事では、就労移行支援と就労継続支援の違いをはじめ、就労系サービスを利用したい方がどのようにして自分に合う支援を選べばよいかを解説します。
また、開業を検討している方向けに就労系サービスの現状もお伝えします。
目次
就労移行支援と就労継続支援の違いとは?

就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)は、どちらも障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスです。
両者の間には、目的や対象者、報酬の有無などの違いがあります。
就労移行支援は企業などへの就職を希望する人が対象で、スキルを習得するための訓練のほか、職場探しや職場定着に向けた支援を行います。
一方の就労継続支援は、企業への就職が難しい人に生産活動の機会を提供したり、就労のために必要な訓練を行ったりします。
▼就労移行支援と就労継続支援の違い
| 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
|---|---|---|---|
| 施設数(全国)※1 | 3,055 | 4,132 | 1万4,926 |
| 目的 | 就職に必要なスキル習得 | 生産活動の機会提供や就労のための訓練 | 生産活動の機会提供や就労のための訓練 |
| 対象者 | 一般企業への就職を希望する障害者 | 一般企業への就職が困難な障害者 | 一般企業への就職が困難な障害者 |
| 対象年齢 | 18歳以上65歳未満※2 | 18歳以上65歳未満※2 | なし |
| 雇用契約 | なし | あり | なし |
| 賃金(工賃) | 基本なし | 平均賃金(月額) 8万1,645円※3 |
平均工賃(月額) 1万6,507円※3 |
| 利用期間 | 原則2年 | 定めなし | 定めなし |
※1 出典:「参考資料」(厚生労働省)
※2 18歳未満や65歳以上でも条件を満たせば利用可能
※3 出典:「令和3年度工賃(賃金)の実績について」(厚生労働省)
それでは就労移行支援と就労継続支援の違いについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
施設数
2021(令和3)年4月の国保連データによると、就労移行支援の施設数は3,055、就労継続支援A型は4,132、同じくB型は1万4,926でした。
就労移行支援は2018(平成30)年度を境に施設数が減少しつつあります。
就労継続支援A型の施設数は2016(平成28)年度までは大きく増加し、その後は落ち着いている状況です。
対して就労継続支援B型の施設数は、毎年度増加が続いています。
目的
就労移行支援の目的は、生産活動や職場体験等の活動の機会の提供と、その他の就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行うことです。
また、求職活動の支援や対象者の適性に応じた職場の開拓も行います。
対象者が職場に定着することを目指しているため、必要があれば就職後の相談も可能です。
就労継続支援はA型・B型ともに生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識と能力を向上するための訓練等を行います。
ただし、雇用契約の締結があるのはA型のみです。
また、就労継続支援では通常の事業所への求職活動支援は行わず、あくまで就労の機会を提供することが目的となっています。
対象者
就労移行支援の対象者は、通常の事業所に雇用されることが可能な障害者(精神障害や知的障害、発達障害、身体障害など)で、一般企業で就労したいと考えている人です。
障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等がある人も対象となります。
就労移行支援が利用可能かどうかは、障害者手帳や医師の意見書などに基づき、地方自治体によって判断されます。
一方、就労継続支援の対象になるのは、通常の事業所に雇用されることが難しい障害者です。
また、2022(令和4)年1月時点における各サービスの利用者数は以下のようになっています。
- 就労移行支援:3万4,877人
- 就労継続支援A型:7万8,695人
- 就労継続支援B型:30万2,545人
対象年齢
就労移行支援と就労継続支援A型を利用するにあたっては、18歳以上64歳未満という対象年齢が決まっています。
ただし、2018(平成30)年4月からは要件を満たせば65歳以上でも利用可能です。
一般的な高校生だと年齢的に利用できませんが、通信制高校や定時制高校に通っている場合は利用を認められるケースがあります。
なお、就労継続支援B型には年齢制限がありません。
雇用契約
就労移行支援は働くために必要な訓練を提供したり求職活動の支援を行ったりするものですから、事業所と利用者の間に雇用契約はありません。
就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、労働の対価として賃金が発生します。
就労継続支援B型では雇用契約を結びませんが、成果報酬として工賃が支払われます。
賃金(工賃)
就労移行支援は職業訓練の意味合いが強く、基本的に賃金や工賃のような労働対価はありません。
2021(令和3)年度の就労継続支援A型とB型の平均賃金(工賃)は以下のとおりです。
▼就労継続支援A型・B型の平均賃金(工賃)
| 就労継続支援A型の平均賃金 | 8万1,645円 | 926円 |
| 就労継続支援B型の平均工賃 | 1万6,507円 | 233円 |
平均賃金(工賃)の推移を見ると、A型とB型ともに増加傾向にあります。
ただし、都道府県ごとで金額にはバラツキがあります。
就労継続支援A型の平均賃金最高額は東京都の9万9,335円、最低額は宮崎県の6万7,570円です。
同じくB型では、最高額は福井県の2万2,093円、最低額は大阪府の1万2,786円となっています。
利用期間
就労移行支援の利用期間は原則2年以内と定められています。
ただし、やむを得ない事情等により期間の延長を希望する場合は、管轄の自治体に延長申請を出すことが可能です。
申請が認められれば最長で12ヶ月間の延長ができます。
就労継続支援においては、A型もB型も利用期間の定めはありません。
就労移行支援と就労継続支援のどっちを選ぶべき?
働く準備ができている人で一般企業への就職を希望しているのなら、就労移行支援を活用してください。
もし一般就労が難しいようなら、就労継続支援の対象者となっているかをチェックしたうえで、利用を検討するとよいでしょう。
働く準備ができている人は就労移行支援を活用
働く準備ができているかどうかは、「就労準備性ピラミッド」を基に作成した以下のチェックリストで確認できます。
就労準備性ピラミッドとは、障害の有無にかかわらず就業する際に必要な5項目を、優先順位順に並べたものです。
目安は20項目中16項目程度です。
(1)健康管理
- 自分の障害や特性を理解できている
- 必要に応じて休息することができる
- だいたい決まった時間に起床・就寝している
- だいたい決まった時間で1日3食をとっている
日常生活管理
- 身だしなみを整えて清潔な状態でいられる
- 趣味など余暇の過ごし方を持っている
- 適切な金銭管理ができる
- 交通機関を利用できる
対人スキル
- あいさつや返事ができる
- 状況に応じた言葉遣い、態度、マナーなどがわかる
- 相手の話を聞いて意図を理解できる
- 自分から話しかけて要件が伝えられる
基本的労働習慣
- 目標や意欲を持って働ける
- 指示または手順どおりに作業ができる
- 指導や助言を受け入れられる
- 報告・連絡・相談ができる
職業適性
- 一定の時間、集中して作業を続けられる
- 時間意識を持って正確に仕事をこなせる
- 業務に慣れれば作業効率が高められる
- 作業内容や手順などの変化に対応できる
一般就労が難しい人は就労継続支援の利用を検討
一般就労が難しい場合は、まず就労継続支援の利用対象かどうか確認しましょう。
以下、厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」からの引用です。
- 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
- 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
- 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
- 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
- 1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
特に50歳以上になって、年齢的または体力的に一般企業での雇用が難しくなった人には、希望に応じて就労継続支援B型を利用することをおすすめします。
それ以外の人は、就労移行支援事業所などで就労アセスメントを受け、自分に合ったサービスを検討してみましょう。
就労アセスメントとは、就労継続支援B型の利用希望者に対して就労面の評価を行うことです。
就労アセスメントプログラムでは「導入期」「適応期」「実践期」の各段階で作業能力の確認と面談を繰り返します。
アセスメントを通じて得られた対象者の情報は、その後の就労支援に携わる各機関によって共有・活用されます。
就労系障害福祉サービスの現状と今後

就労移行支援・就労継続支援を含む就労系障害福祉サービスを経て、民間企業に就職する人の数は年々増加しています。
2020(令和2)年は約1.9万人が一般就労への移行を実現しました。
しかし、厚生労働省の社会保障審議会障害者部会では、以下のような課題が指摘されています。
- 就労系障害福祉サービス利用者の就労能力や適性を客観的に評価し、適切な支援内容に活用する手法が確立されていないため、利用者本人や支援者の就労能力および一般就労可能性の把握が不十分である。
- 就労系障害福祉サービスは原則的に一般就労中の利用は想定していないが、多様な就労ニーズを踏まえて一般就労への移行促進や雇用継続を図るために、一般就労中の企業における支援と就労系障害福祉サービスによる支援の連携を強化する必要がある。
- 障害者の就労支援に携わる人材の質・量ともに不足しており、実践的な研修機会も限られている。
- 一般就労後の定着支援の円滑化のために地域の支援機関の連携強化が必要。
- 重度障害者等の就労支援については、今後に向けた検討が必要である。
こういった指摘を受け、国は現在、新しい就労アセスメントサービスや一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用などについて検討を行っています。
就労アセスメントサービスが創設されれば、以下のように現状の課題を改善することが期待できます。
- 就労系障害福祉サービス利用前の課題
- 申請段階でサービスを選択しなければならないが、選択に必要な情報の把握や自己理解が難しい。
→事前に自身の強みや課題、配慮事項等を整理した上でサービスを選択できる。
- 就労系障害福祉サービス利用段階の課題(1)
- 就労する事業所がアセスメントを実施するため、他の選択肢を持ちにくい。
→就労する事業所とアセスメントを実施する事業所が異なるため、自由な選択肢が持てる。
- 就労系障害福祉サービス利用段階の課題(2)
- 就労ニーズや能力等が変化しても他の選択肢を検討しづらい。
→支給決定更新までの間にアセスメントを実施して、就労ニーズや能力等の変化に応じた選択も可能になる。
また、一般就労後の就労系サービスの利用が可能になった場合にもメリットがあります。
短時間勤務と就労系福祉サービスを一時的に並行して利用すれば、段階的に企業での勤務時間を増やすことが可能です。
安定して勤務できるために必要な訓練や支援を受けられるようにもなるでしょう。
就労継続支援B型の開業を目指すならミライクス
今回は3つの就労系障害福祉サービスについて解説しました。
その中でも就労継続支援B型は、利用者数・施設数・国の予算とも年々増加しつつあり、ニーズの高さがうかがえます。
就労継続支援B型は長期にわたって利用される施設であり、経営的観点からは収益性と安定性が高い事業といえます。
これから新規参入したとしても大きなビジネスチャンスを得ることができるでしょう。
もし就労継続支援B型の開業を検討されているなら、ミライクス開業の「就労継続支援B型実践講座」がおすすめです。
約6ヶ月間にわたる合計4回の研修を通して開業準備を進めることができます。
開業後のロイヤリティは発生せず、コンサルティング費用も他社サービスと比較してリーズナブルです。
まずは無料セミナーへご参加ください。
- 「参考資料」(厚生労働省)
- 「令和3年度工賃(賃金)の実績について」(厚生労働省)
- 「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」(厚生労働省)
- 「障害者の就労支援対策の状況」(厚生労働省)
- 「障害者の就労支援について③」(厚生労働省)
- 「改定版・就労移行支援事業所による就労アセスメント実施マニュアル」(厚生労働省)
- 「障害福祉分野の最近の動向」(厚生労働省)