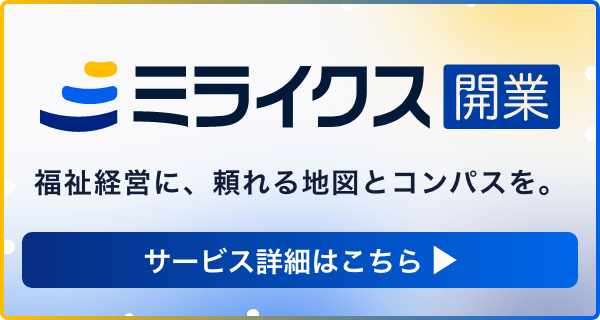事業を探す
2023.9.2
2023.8.9
相談支援専門員とは?資格要件や待遇、仕事内容について解説

相談支援専門員とは、障害のある方が暮らしやすくなるように相談、支援を行い、障害福祉サービスとの間をつなぐ職種です。
また、障害のある方が地域社会で暮らしていくためのサポートも行います。
相談支援専門員は無資格から目指せますが、一定の実務経験と研修の受講が必要となります。
この記事では、相談支援専門員の役割・仕事内容から、2023(令和5)年現在の資格要件、年収や向いている人などについて詳しく解説します。
目次
相談支援専門員とは?
相談支援専門員とは、障害者が自立した日常生活、または社会生活を送れるようにサポートをする仕事です。
障害者や家族の悩みごとを聞き、必要な障害福祉サービスとの橋渡しをしたり、その他さまざまな困りごとの相談に乗ったりして、障害者を支援します。
勤務先は、主に基幹相談支援センターや相談支援事業所、市区町村の福祉窓口などです。
- 基幹相談支援センター
-
地域の相談支援機関の中核となる施設で、相談支援事業所への専門的指導や人材育成支援なども担います。
障害の種別や対象者にかかわらず対応するので、利用者にとっては相談先がわからないときにも頼りになります。
- 相談支援事業所
-
障害者や家族に必要な情報を提供し、障害福祉サービスの利用や地域社会での暮らしをサポートする機関です。
基幹相談支援センターに相談した利用者を引き継ぎ、フォローする場合もあります。
なお、指定特定相談事業所・指定障害児相談支援事業所数に配置されている相談支援専門員の数は、2019(平成31)年4月1日時点で全国に2万2,631人です。
- 市区町村の福祉窓口
- 各市区町村の障害福祉課などに設けられている相談窓口で、障害福祉サービス等の利用計画の作成や地域生活への移行に向けた支援などを行っています。
相談支援専門員の仕事内容

相談支援専門員が対応する業務は、その対象者や相談内容によって次の4つに分類されます。
- 基本相談支援
- 地域相談支援
- 計画相談支援
- 障害児相談支援
続いては、その内容について1つずつ解説します。
1.基本相談支援
基本相談支援は、相談支援事業のベースとなる仕事です。
障害者やその家族の現状、困りごとや希望などをヒアリングして、どのような障害福祉サービスを利用するのが良いかなどの情報を提供します。
次に説明する地域相談支援や計画相談支援、障害児相談支援をつなぐ役割です。
2.地域相談支援
地域相談支援は、障害者が地域社会で自立した生活を送れるように支援する仕事で、地域移行相談支援と地域定着支援に分けられます。
- 地域移行相談支援
障害者支援施設や精神科病院に入所・入院している障害者が施設を退所するにあたって、地域で暮らしていくための住居探しや必要な手続き、準備などを行います。
- 地域定着支援
-
すでに施設を退所している方が再び施設に戻ることなく地域で暮らしていくためのサポートをします。
24時間体制で連絡を受け付け、緊急時の対応も行います。
対象となるのは、一人暮らしの障害者、または同居家族の病気や障害のために緊急時に支援が得られない障害者です。
3.計画相談支援
障害者の悩みや困りごと、希望を聞き取り、一人ひとりに合った障害福祉サービスを利用できるように調整する「サービス利用支援」が業務のひとつです。
障害福祉サービスの利用申請時に「サービス等利用計画案」を作成し、自治体が支給決定した後はサービス提供事業者と連絡を取り合い、障害者がサービスを利用できるように調整します。
さらに「継続サービス利用支援」として、一定期間ごとにサービス等利用計画を見直すモニタリングを行い、必要であればサービス利用の更新やサービス等利用計画の変更を行います。
4.障害児相談支援
児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を希望する障害児や、その家族の相談に応じる業務です。
それぞれの家庭の悩みや困りごと、希望に合わせたサービスを提供できるように検討し、障害児支援利用計画案を作成します。
自治体が支給決定した後は、障害児支援利用計画を作成し、サービス提供事業者との連絡、調整を行います。
この一連の業務が「障害児支援利用援助」と呼ばれるものです。
利用を開始したサービス内容を、一定期間ごとにモニタリングして見直し、必要があれば障害児支援利用計画を変更する業務を「継続障害児支援利用援助」といい、同じく障害児相談支援業務の一つとなっています。
相談支援専門員になるには資格が必要?

相談支援専門員は、無資格からも目指せる職種です。
とはいえ、一定の実務経験は必要となりますし、相談支援従事者初任者研修の修了も相談支援専門員になるための要件となっています。
また、相談支援専門員として職務に就いた後も、5年ごとに相談支援従事者現任者研修を受講し、修了する必要があります。
相談支援専門員のキャリアパスとして、主任相談支援専門員へのステップアップも可能です。
主任相談支援専門員になるには、現任者研修修了+3年以上の実務経験+主任研修修了が求められます。
続いて、それぞれの内容について詳しく解説します。
相談支援専門員に必要な実務経験
相談支援専門員になるための実務経験年数は、保有資格や業務内容によって異なります。
- 相談支援業務 5年以上
- 介護等の業務 10年以上
- 有資格者 3年以上または5年以上
1.相談支援業務を行っている場合…5年(900日)以上
相談支援業務とは、以下のような内容を指します。
- 施設等での相談支援業務
- 医療機関での相談支援業務
- 就労支援に関する相談支援業務
- 特別支援教育における進路相談・教育相談
- その他都道府県知事が上記の業務に準ずると認めた業務
なお、医療機関での相談支援業務は、以下に該当する方に限定されています。
(1)社会福祉主事任用資格保持者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者
(3)医師・保健師・看護師・理学療法士・社会福祉士などの国家資格保持者
(4)施設での相談支援業務経験が1年以上の方
(3)の国家資格が必要な業務に5年以上従事している方は、必要な実務経験が3年(540日以上)に短縮されます。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
また、2006(平成18)年9月30日以前に
- 障害児相談支援事業
- 身体障害者相談支援事業
- 知的障害者相談支援事業
- 精神障害者地域生活支援センター
で相談支援業務を行っていた方は、通算3年以上の実務経験があれば相談支援従事者初任者研修を受講可能です。
2.介護等の業務を行っている場合…10年(1,800日)以上
介護等の業務とは、以下のような内容を指します。
- 医療機関または施設における介護業務
- その他都道府県知事が上記の業務に準ずると認めた業務
なお、介護等の業務に従事している方の中でも、以下の資格を保有している方は必要な実務経験年数が3年または5年に短縮されます。
- 国家資格等が必要な業務に5年以上従事している方…3年以上
- 社会福祉主事任用資格等(※)を保有している方…5年以上
※社会福祉主事任用資格者等:社会福祉主事任用資格を保有する方、介護職員初任者研修に相当する研修を修了した方、保育士、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者
相談支援従事者初任者研修
先にお伝えした実務経験要件を満たし、なおかつ相談支援従事者初任者研修を修了すれば相談支援専門員として働けるようになります。
相談支援従事者初任者研修は、各都道府県で実施されています。
研修プログラムは計7日間、42.5時間の講義と演習、そして計2ヶ月間の実習からなるものです。
以下に、カリキュラムの例を挙げて、もう少し詳しく解説します。
▼相談支援従事者初任者研修のカリキュラム例
| 研修1日目 | 講義 |
|
|---|---|---|
| 研修2日目 | ||
| 研修3日目 | 演習 | グループ演習(関係性構築、インテーク・アセスメントなど) |
| 研修4日目 | ||
| 実習 (約1ヶ月) |
グループ演習(関係性構築、インテーク・アセスメントなど) | |
| 研修5日目 | 演習 | グループ演習(サービス等利用計画案作成演習など) |
| 実習 (約1ヶ月) |
先の実習で扱った実践例を再度アセスメントし、サービス等利用計画案を作成 | |
| 研修6日目 | 演習 | 実習の振り返りなど |
| 研修7日目 | 演習 |
|
参考:「令和4年度大阪府相談支援従事者初任者研修(7日課程)募集要項」(社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団)
以上のすべての日程をこなし、数々の課題を提出するとようやく修了証書が交付されます。
研修日数や1年間に開催される回数、受講費用は自治体により異なりますので、事前に確認することをおすすめします。
相談支援従事者現任研修
相談支援専門員の資格を継続し、技能を高めていくためには、初任者研修を受講した翌年度から5年度ごとに1回以上、相談支援従事者現任研修を受講する必要があります。
現任研修を受けるタイミングは、初任者研修を受けた年を起点として考えます。
その翌年から5年間が第1期間、次の5年間が第2期間となり、1期間のうちに1回以上現任研修を受けなければなりません。
相談支援従事者現任研修も初任者研修と同様に各都道府県単位で実施されており、その内容は計4日間(24時間)の講義と演習、そして約1ヶ月の実習に参加するプログラムです。
以下にカリキュラムの事例を示しますので、参考にしてください。
▼相談支援従事者現任研修のカリキュラム例
| 研修1日目 | 講義 |
|
|---|---|---|
| 研修2日目 | 演習 |
|
| 実習 (約1ヶ月) |
実践例の課題に対する支援を行う | |
| 研修3日目 | 演習 |
|
| 実習 (約1ヶ月) |
|
|
| 研修4日目 | 演習 |
|
参考:『「相談支援従事者研修事業の実施について」の改正について』(厚生労働省)
参考:「令和4年度大阪府相談支援従事者現任研修募集要項」(社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団)
初任者研修と同様、自治体によって研修日数や内容、受講料に差があります。
ご自身の地域の研修内容を事前に確認したうえで、受講しましょう。
相談支援従事者主任研修
主任相談支援専門員は、地域づくりや人材育成、困難事例の対応が可能で、なおかつ地域の中核的な役割を担う専門職として2018年に創設されました。
- 相談支援専門員のキャリアパスを作ること
- 人材を多層化することで役割の整理をすること
- 相談支援専門員自体や提供するサービスの向上を目指すこと
を目的としています。
大阪府の場合、
- 障害者等への相談支援業務に関して、十分な知識と経験を有する相談支援専門員である
- 現任研修を修了し、相談支援または障害児相談支援の業務に3年以上従事している
の2点に加え、さらに以下のいずれかの要件を満たす人が主任研修の対象となります。
(1)基幹相談支援センターまたはそれに準ずる機能を有する相談支援事業所等において現に相談支援に関する指導的役割を担っている
(2)都道府県における相談支援従事者研修またはサービス管理責任者研修において研修の企画に携わっている、または講義・演習に講師として携わっている
(3)相談支援専門員の業務に関して十分な知識と経験を有し、大阪府または市町村が適当と認める者である
相談支援従事者主任研修では、30時間の講義と演習を受けます。
▼相談支援従事者主任研修のカリキュラム例
| 研修1日目 | 講義 |
|
|---|---|---|
| 研修2日目 | 講義 演習 |
|
| 研修3日目 | 講義 演習 |
|
| 研修4日目 | 講義 演習 |
|
| 研修5日目 | 演習 |
|
要件やカリキュラムの詳細は自治体により異なる可能性があるため、ご自身の地域で確認されると良いでしょう。
相談支援専門員の仕事はつらいってホント?
2013(平成25)年に実施された「相談支援に係る業務実態調査」によると、相談支援専門員の約46%が経験5年未満のスタッフだという結果でした(※)。
その結果から見ても、相談支援専門員の定着率が低いことは事実だと考えられます。
相談支援専門員は、やりがいのある仕事だといわれる一方で、「つらい」と感じる場面があるのも事実です。
特に「仕事内容と給与が見合わない」「対応困難なケースに疲れてしまう」といった声が多く聞かれます。
続いては、相談支援専門員の勤務条件や困難な点についてお伝えします。
※「平成25年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 相談支援に係る業務実態調査 報告書」(日本相談支援専門員協会)
相談支援専門員の年収
厚生労働省の調査によれば、2021(令和3)年9月時点の相談支援専門員の平均給与額(平均月額)は常勤で35万8,010円、非常勤で15万8,330円です(※)。
福祉・介護職員処遇改善加算等の届出をしている事業所が増えており、令和2年9月と令和3年9月の給与を比較すると、常勤で1万700円、非常勤でも5,870円上がっています。
平均給与額から年収を算出すると、常勤では約430万円、非常勤だと約190万円となります。
同じ年の調査結果から算出した年収を比較すると、
- サービス管理責任者等:約497万円
- 障害福祉サービス等従事者全体:約432万円
- 地域生活支援員:約392万円
なので相談支援専門員の年収は数字だけ見れば悪くはありません。
出典:※出典:「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(厚生労働省)
※平均給与額は、基本給+手当+一時金(10〜3月支給金額の1/6)により算出。
相談支援専門員の勤務時間
2021(令和3)年に行われた調査によると、相談支援専門員の1日あたりの業務時間は、平均537.6分(約8時間57分)でした。
詳しく見ると、540分以上600分未満(9時間以上10時間未満)が40.1%と最も多く、480分以上540分未満(8時間以上9時間未満)が35.8%と続きました。
平均業務時間から兼務業務や休憩などを除き、相談支援業務にかけた時間を算出すると、424.3分(約7時間4分)となりました。
出典:出典:「相談支援事業所及びその従業者の業務実態把握及び相談支援事業の在り方を検討する調査研究 報告書」(一般社団法人北海道総合研究調査会)
支援が難しいケースの存在
経験が浅い相談支援専門員を悩ませるのが、支援困難事例と呼ばれるケースです。
支援困難事例とは、相談支援専門員にとって負担感が大きい事例のことです。
「相談支援に係る業務実態調査」によれば、回答者の8割(82.6%)が1年間に対応困難事例があったと回答しています(※1)。
困難事例の問題領域は多岐に及び、この調査では
- 金銭、財産管理
- 不安解消、情緒安定
- 人間関係に関すること
が多く見られました。
2020(令和2)年に福岡市で行われた調査では、サービスにつながりにくいケースの中でも
- 多問題家族(複数の問題を同時に抱える家族)
- カスタマーハラスメント
- 金銭トラブル
などの延べ支援件数が増加しています(※2)。
相談実人数に対する困難事例の割合は高くないものの、このような対応困難事例と向き合うことが、少なからずストレスとなっていることも事実でしょう。
※1 出典:「平成25年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 相談支援に係る業務実態調査 報告書」(日本相談支援専門員協会)
※2 出典:「福岡市の相談支援体制に関する提言書(案)」(福岡市障がい者等地域生活支援協議会 相談支援部会)
相談支援専門員に向いている人は?
ここまで相談支援専門員になるためのステップや、相談支援専門員の就労状況などについて解説してきました。
続いては、どのような人が相談支援相談員に向いているのか、その資質について解説します。
相談支援員に向いている人の特徴として、以下の3点が挙げられます。
1.傾聴力、コミュニケーション力が高い人
相談支援員は、利用者の話を親身になって聞き、悩みや困りごと、希望などについて相手の立場で理解しなければなりません。
ですから、相手の話をじっくりと聞き取って信頼関係を築き、相手の本音を引き出せるコミュニケーション能力が必要となります。
2.相手を尊重できる人
相談支援員は、あくまでも利用者に寄り添いながら動く立場です。
良かれと思ったことでも、利用者が望むとは限りません。
利用者を尊重し、本人や家族が望む生活が送れるように支援することが大切です。
3.向上心がある人
先に挙げたような能力を持ち合わせている人でも、ほかの相談員などの様子を見たりアドバイスを受けたりして、相談技術や対応の質を向上させていく意欲が大切です。
また、福祉関連の法律や現場の様子は、刻々と変わっていきます。
そのような状況に対応し、常に勉強してキャッチアップすることを怠らない姿勢も求められます。
相談支援専門員の将来性
現在、市区町村の障害者相談支援事業はすべての自治体で実施されています。しかし、その内容や規模はさまざまで、自治体によるばらつきが見られるのが現状です。
相談支援の種類別に見ると、計画相談支援や障害児相談支援は利用者数・事業所数・従事者数ともに増加傾向にあります。
一方、基幹相談支援センターについてはまだ45%ほどの市区町村でしか設置されていません。
しかし、2022(令和4)年12月10日に成立した障害者総合支援法の改正法により、基幹相談支援センターの整備が市町村の努力義務となりました。
その影響もあり、相談支援専門員に対するニーズは高い状況が続くと考えられます。
相談支援専門員は今後も量・質ともに向上が求められる需要の高い仕事だといえるでしょう。
障害福祉サービスを開業するならミライクス
相談支援専門員は主任相談支援専門員を目指すこともできますが、ほかの障害福祉サービスでそのキャリアを活かすことも可能です。
相談支援専門員として5年以上の実務経験があれば、障害児通所支援の児童発達支援管理責任者や障害福祉サービスのサービス管理責任者を目指せます。
障害福祉サービスを開業し、管理者とサービス管理責任者を兼任すれば、人件費を削減し、利益率の高い事業所を経営することも可能でしょう。
ミライクスは、放課後等デイサービスや就労継続支援B型、共同生活援助(障害者グループホーム)の開業支援を行っています。
約半年間の研修を受ける中で、障害福祉サービスの開業・経営に必要なノウハウを習得できます。
ロイヤリティも必要ないので、開業後のキャッシュフローに影響することもありません。
障害福祉サービスの開業に興味のある方は、まずはお問い合わせください。
- 「相談支援の現状と課題」(厚生労働省)
- 「障害のある人に対する相談支援について」(厚生労働省)
- 「相談支援従事者初任者研修の受講条件となる実務経験一覧表」(福井県)
- 「東京都における相談支援従事者等研修について」(東京都)
- 「相談支援専門員の資質の向上について」(厚生労働省)
- 「福岡市の相談支援体制に関する提言書(案)」(福岡市障がい者等地域生活支援協議会 相談支援部会)
- 「障害者総合支援法等の改正について」(厚生労働省)
- 「指定計画相談支援の提供に当たるものとして厚生労働大臣が定めるもの」(厚生労働省)
- 「令和4年度大阪府相談支援従事者初任者研修(7日課程)募集要項」(社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団)
- 「相談支援従事者研修について」(大阪府)
- 「平成25年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 相談支援に係る業務実態調査 報告書」(日本相談支援専門員協会)
- 「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(厚生労働省)
- 「相談支援事業所及びその従業者の業務実態把握及び相談支援事業の在り方を検討する調査研究 報告書」(一般社団法人北海道総合研究調査会)