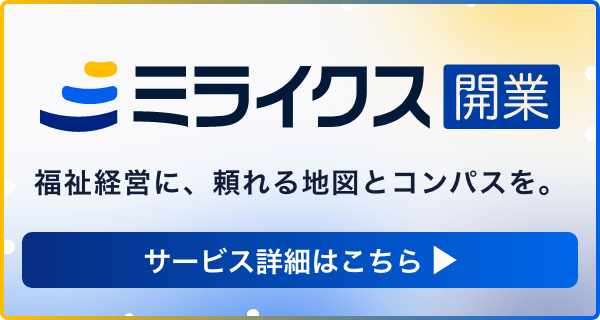事業を探す
2023.11.18
2023.10.25
サービス管理責任者(サビ管)とは?仕事内容から資格取得の流れまで詳しく解説!

サービス管理責任者(略:サビ管)は、障害福祉施設における全体管理を行う職員のことです。
主に、障害のある人が適切なサービスを受けるための支援プロセスの管理、従業員に対する技術的な指導、各所との連携といった業務に携わります。
サービス管理責任者になるには、3~8年の実務経験を積んだ上で基礎研修・実践研修の2つの研修を受講しなくてはなりません。
この記事では、サービス管理責任者の具体的な仕事内容や勤務先、サービス管理責任者になるために必要となる資格とその要項、研修の流れを詳しく解説していきます。
目次
サービス管理責任者(サビ管)とは?
サービス管理責任者とは、障害福祉サービスを提供する事業所におけるサービス品質向上のために、障害者総合支援法に基づいて配置が義務付けられている管理職です。
主な役割としては、
- 利用者のニーズに応じたサービス提供の計画立案・実行
- サービス提供に関する記録の管理
- 職員の指導・教育
- サービスに関する相談や苦情の受付・対応
- 各関係機関との調整
などがあります。
サービス管理責任者には現場での豊富な実務経験はもちろん、利用者や職員とのコミュニケーション能力、問題解決能力、人材管理能力が必要です。
仕事内容
サービス管理責任者の主な仕事は以下の3つです。
- 支援プロセスの管理(個別支援計画書の作成・実施)
- 職員の指導やサポート
- 関係機関との連携
ここでは、それぞれの仕事内容を簡単に解説します。
1. 支援プロセスの管理(個別支援計画書の作成・実施)
サービス管理責任者の重要な仕事の1つが支援プロセスの管理です。
具体的には、
- 障害者向けサービス利用者がどのような障害を持っているのか
- どのような支援が必要なのか
- 今後どうしていきたいのか
といった観点から個別支援計画を立てて支援します。
個別支援計画書の作成と実施のほか、個別支援計画を作成するために家族との面談や職員との会議の場を設定したり、サービスの開始後は計画の見直し・修正を行ったりします。
2. 職員の指導やサポート
サービス管理責任者のもう1つの重要な仕事は、職員の指導やサポートです。
職員のリーダー的存在として経験の浅い職員の指導やサポートを行うと同時に、施設全体のサービス向上を図ります。
職員研修などにも関わり、スキルアップや資格取得ができるよう支援します。
施設内のチームマネジメントと人材育成に率先して取り組む立場です。
3. 関係機関との連携
障害福祉サービスは1つの施設だけで完結するものではなく、医療機関や行政機関、その他の関連事業所との連携が不可欠です。
サービス管理責任者は関係機関とコミュニケーションを取り、サービスの質が担保できるよう調整します。
また、有事の際にも円滑に対応できる体制を整えておかなければなりません。
主な勤務先
サービス管理責任者の勤務先は
- 入所系事業所
- 通所系事業所
- 勤労支援事業所
の3種に分かれます。
勤務先ごとに下記のような配置基準が定められています。
▼サービス管理責任者の配置基準
| 事業所区分 | 勤務先 | 配置基準 |
|---|---|---|
| 通所系事業所 |
|
利用者60人に1人以上 (以降40人増すごとに1人追加) |
|
||
| 入所系事業所 |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
| 就労支援事業所 |
|
利用者30人につき1人以上 (以降30人増すごとに1人追加) |
|
||
|
||
|
サービス管理責任者になるには?どんな資格が必要?

サービス管理責任者になるためには、相談支援業務や直接支援業務などの実務経験を経たうえで、2度の研修を受講しなければなりません。
まず、定められた実務経験期間を終えてから26時間にわたる基礎研修を受けます。
さらに2年間の実務経験(一部業務)を積み、14.5時間の実践研修まで完了すれば、サービス管理責任者として正規配置されるといった流れです。
▼サービス管理責任者になるまでの流れ
1. 実務経験
- 相談支援業務:5年
- 直接支援業務:8年
- 資格保有者としての直接支援業務:5年
- 国家資格業務3年+相談支援または直接支援業務:3年
2. 基礎研修(26時間)
※サービス管理責任者等の一部業務(個別支援計画原案の作成)が可能になる
3. 2年の実務経験(OJT)※
4. 実践研修(14.5時間)
5. サービス管理責任者等の正規配置(5年ごとに要更新)
※基礎研修受講開始時において、実務経験者が障害福祉サービスの個別支援計画の作成の業務に従事する場合は6ヶ月以上
現在は新しい制度への移行期間であるため、やむを得ない事由によりサービス管理責任者の欠員がある場合には、基礎研修修了者をサービス管理責任者とみなして配置する「みなし配置」をすることが可能です。
- 実務経験要件を満たしていること
- サービス管理責任者等の欠如以前からその事業所に配置されており、欠如時にすでに基礎研修を修了していること
ただし、みなし配置が可能な期間は実践研修修了までの最長2年で、期間経過後の継続配置には研修修了要件を満たす必要ががあります。
通常の方法でサービス管理責任者になるには、業務ルートによって期間が異なりますが、最低でも下記に示す年数が必要です。
- 相談支援業務ルート…7年
- 相談支援業務5年 → 基礎研修 → 実務経験(OJT)2年 → 実践研修
- 直接支援業務ルート…10年または7年
-
(1)直接支援業務8年 → 基礎研修 → 実務経験(OJT)2年 → 実践研修…10年
(2)資格保有者としての相談支援・直接支援業務5年 → 基礎研修 → 実務経験(OJT)2年 → 実践研修…7年
- 国家資格ルート…5年
- 国家資格業務3年(うち3年は相談支援または直接支援業務)+基礎研修+実務経験(OJT )2年+実践研修
次の項では、実務経験の要件と研修の受講について詳しく解説します。
実務経験の要件
サービス管理責任者になる要件として、障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野に関わる支援業務において3〜8年の実務経験が必要です。
実務経験の種類は
(1)相談支援業務での実務経験
(2)直接支援業務での実務経験(有資格者としての実務経験を含む)
(3)国家資格保有者としての実務経験
の3つに分けることができます。
経験年数は、それぞれの業務内容や所有資格によって異なります。
| 実務経験の種類 | 必要経験年数 |
|---|---|
| (1)相談支援業務での実務経験 | 5年以上 |
| (2)直接支援業務での実務経験 | 8年以上 |
| (3)国家資格保有者としての実務経験 | 5年以上 ※国家資格保有者は3年以上 |
以下、各業務について見ていきましょう。
(1)相談支援業務
相談支援業務とは、主に障害者に対して日常生活の自立に関する相談や助言、指導などのサポートを行う業務のことです。
以下のいずれかの相談支援業務において、5年以上の実務経験が必要となります。
- 相談機関・施設等で相談支援業務に従事
- 保険医療機関で相談支援業務に従事しており、次のいずれかに該当
- (1)社会福祉主事任用資格保有者
(2)介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)に相当する研修を修了した者
(3)国家資格(※) 保有者
(4)施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事した期間が1年以上
- 就労支援に関する相談支援の業務に従事
※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
具体的には、次のような職業での実務経験が該当します(上記※の保険医療機関で相談支援業務に従事する職業は割愛)。
- 相談支援専門員
- ソーシャルワーカー
- 医療ソーシャルワーカー
- ケアマネジャー
- 生活相談員
- 支援相談員
(2)直接支援業務
直接支援業務とは、主に障害者に対して入浴・排泄・食事などの身体介護や日常生活における基本的動作の指導・知能技能の付与、生活能力の向上のための訓練やサポートを行う業務のことです。
以下のいずれかでの経験が8年以上必要になります。
資格取得以前の直接支援業務も経験年数に含めてかまいません。
- 施設及び医療機関等において介護業務に従事
- 障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事
- 盲学校・聾学校・養護学校における職業教育の業務に従事
- その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事
具体的には、次のような職種での実務経験が該当します。
- 生活支援員
- 指導員
- 介護職員
- 看護助手
(3)資格保有者としての相談支援・直接支援業務
以下の資格保有者は、5年以上の直接支援業務における実務経験が必要です。
- 社会福祉主事任用
- 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)相当
- 児童指導員任用
- 保育士
- 精神障害者社会復帰施設指導員任用
以下の国家資格保有者については、3年以上の相談支援または直接支援業務の実務経験に加え、3年以上の国家資格による業務経験が必要となります。
ただし、相談支援業務・直接支援業務における実務経験の期間と、国家資格による業務経験の期間が重複しても問題ありません。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 視能訓練士
- 義肢装具士
- 歯科衛生士
- 言語聴覚士
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師
- きゅう師
- 柔道整復師
- 栄養士(管理栄養士)
- 精神保健福祉士
実務経験として認められる業務の範囲については、都道府県ごとに独自の基準が設けられている場合があります。
管轄自治体の担当部署(福祉課など)に問い合わせて確認しておくことが必要です。
研修受講の要件
サービス管理責任者になるために必要な研修は「基礎研修」と「実践研修」の2つです。
また、サービス管理責任者として正規配置された後は、5年ごとに更新研修を受講しなければなりません。
ここでは、基礎研修と実践研修について解説します。
基礎研修
基礎研修は実務経験の要件満了予定から2年間前倒して受講することができます。
2019(平成31)年4月に制度改正が行われ、基礎研修の合計所要時間は26時間に短縮されました。
基礎研修のうち、相談支援従事者初任者研修講義部分では次の3つのパートに分かれた講義が行われます。
▼基礎研修(うち相談支援従事者初任者研修講義部分)
| 講義内容 | 時間数 |
|---|---|
| 障害者の地域支援と相談支援従事者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)の役割に関する講義 | 5時間 |
| 障害者総合支援法・児童福祉法の概要とサービス提供のプロセスに関する講義 | 3時間 |
| 相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義 | 3時間 |
| 合計 | 11時間 |
その後の基礎研修は共通講義と演習です。
▼基礎研修
| 講義内容 | 時間数 |
|---|---|
| サービス管理責任者の基本姿勢とサービス提供のプロセスに関する講義 | 7.5時間 |
| サービス提供プロセスの管理に関する演習 | 7.5時間 |
| 合計 | 15時間 |
基礎研修修了後は、OJTとして個別支援計画の原案作成を行えるようになります。
また、やむを得ない事由によりサービス管理責任者の欠員がある場合には、最長で2年間、基礎研修修了者をサービス管理責任者とみなして配置することも可能です。
実践研修
実践研修は2019(平成31/令和元)年度に新設された制度です。
基礎研修修了者として2年以上の実務経験(OJT)を積むことで受講要件を満たすことができます(※)。
実践研修の内容は下表のとおりです。
▼実践研修
| 講義内容 | 時間数 |
|---|---|
| 障害福祉の動向に関する講義 | 1時間 |
| サービス提供に関する講義と演習 | 6.5時間 |
| 人材育成の手法に関する講義と演習 | 3.5時間 |
| 他職種および地域連携に関する講義と演習 | 3.5時間 |
| 合計 | 14.5時間 |
実践研修を修了すれば、サービス管理責任者等の正規配置を受けられるようになります。
基礎研修修了時と違って業務内容に制限はなく、個別支援計画書の作成・実施のほか、職員の指導やサポート、関係機関との連携といった業務を行うことも可能です。
※基礎研修受講開始時において、実務経験者が障害福祉サービスの個別支援計画の作成の業務に従事する場合は6ヶ月以上
出典:「サービス管理責任者等研修制度について」(厚生労働省)
サービス管理責任者の年収は?

事業所の加算の取得状況によって年収に差は出ますが、障害福祉サービス関連の全事業所におけるサービス管理責任者の年収は以下のとおりとなっています。
| 平均給与額 | 年収(平均給与額×12) | |
|---|---|---|
| サービス管理責任者(常勤) | 388,340円 | 4,660,080円 |
| サービス管理責任者(非常勤) | 207,600円※1 | 2,491,200円 |
| 福祉・介護職員 ※2 | 311,050円 | 3,732,600円 |
出典:「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要」(厚生労働省)
※1 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を取得している事業所
※2 ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員
サービス管理責任者は資格取得の難易度が高いと同時に、関連施設での需要も高いため、福祉業界の職種の中では高年収となる傾向にあります。
障害福祉事業分野での実務経験があってキャリアアップや収入アップを考えているのなら、サービス管理責任者を目指すのがおすすめです。
サービス管理責任者の仕事は大変?1日のスケジュールを調査!
実際のところ、サービス管理責任者の仕事はどのくらい大変なのでしょうか。
あるいは、どんなところにやりがいが感じられるのでしょうか。
現場の声を知るために、10人のサービス管理責任者へアンケート調査を実施しました。
以下、仕事の大変さや仕事のやりがい、1日のスケジュールについて、アンケート調査で得られた回答を紹介します。
実施時期:2023年3月
調査概要:サービス管理責任者として働いている方へのアンケート
調査対象:障害福祉サービス事業所でサービス管理責任者として勤務している方(10名)
調査媒体:クラウドワークス
仕事の大変さ
「サービス管理責任者の仕事は、大変だと思いますか?」という質問に対して、アンケート回答者10人全員が「はい」と答えています。
特にサービス管理責任者としての責任の重さや、その責任の重さからくる仕事への緊張感について言及している人が多くいました。
利用者全員の計画を立てないといけないので、面談が多くスケジュール管理が大変です。(20代女性/就労移行支援)
支援計画をはじめ、文字通りサービス全体の責任を負っているので、責任感の重圧を感じます。(30代女性/就労継続支援B型)
サービス管理責任者の仕事は、常に緊張感のある状況で遂行されるため、大変だと感じることがあります。(20代男性/生活介護)
作業中心になりがちなのでワーカー育成の時間がなかなか持てないのが現状です。(40代女性/就労継続支援B型)
支援計画作成のための面談と書類作成業務の煩雑さから自身のスケジュール管理が大変で、職員の育成が十分にできていないという声も上がっています。
仕事のやりがい
「サービス管理責任者の仕事に、やりがいを感じますか?」という質問に対して、10人中8人が「はい」と回答しています。
利用者との関わりそのものが仕事のやりがいにつながっているようです。
具体的には利用者の成長が感じられたときや、利用者やその家族から感謝の言葉をもらったときを挙げています。
毎月の工賃目標を達成出来た時や、出来なかった作業ができるようになった利用者さんを見た時です。(40代女性/就労継続支援B型)
利用者との関わりを持つことにやりがいを感じます。(40代男性/療養介護)
利用者さまならびにそのご家族から感謝のお言葉をいただいた時に感じます。(50代男性/生活介護)
また、サービス管理責任者として広い観点からアプローチを考えられることに、非常にやりがいを感じていると答えた人もいました。
1日のスケジュール
サービス管理責任者の働き方をよりイメージしやすくするために、アンケート回答者3人が実際にこなしている1日のスケジュールを紹介します。
▼Aさん(40代女性/就労継続支援B型)の1日のスケジュール
| 08:40 | 出勤 |
|---|---|
| 09:00 | 朝礼 |
| 10:00 | 利用者と作業 |
| 12:00 | 昼休憩 |
| 13:00 | 利用者と作業 |
| 15:00 | 利用者面談や連絡調整 |
| 16:30 | 終礼 |
| 17:00 | 個別支援計画の作成や記録、請求関係対応 |
| 19:00 | 退勤 |
※就労移行や就労定着で同行や訪問が入ることがあるそうです(平均勤務時間:10時間20分)
▼Bさん(30代男性/生活介護)の1日のスケジュール
| 08:30 | 出勤 |
|---|---|
| 08:45 | 送迎 |
| 09:45 | 現場および事務作業 |
| 12:00 | 昼休憩 |
| 13:00 | 現場および事務作業、上司に現状報告 |
| 16:00 | 送迎 |
| 17:00 | 個別支援計画の作成および事務作業 |
| 18:45 | 退勤 |
※平均勤務時間:10時間15分
▼Cさん(40代男性/療養介護)
| 08:30 | 出勤 |
|---|---|
| 08:40 | 朝礼 |
| 09:00 | 利用者への挨拶まわり |
| 10:00 | 病棟スタッフとのカンファレンス |
| 11:30 | 昼食の様子を確認 |
| 12:00 | 昼休憩 |
| 13:00 | 利用者記録の確認 |
| 14:00 | ・サービス担当者会議 ・個別支援計画で実施している活動等の様子を確認 |
| 15:00 | 個別支援計画の作成 |
| 17:00 | 夕食の様子を確認 |
| 17:20 | 議事録作成、翌日の日程確認 |
| 18:00 | 退勤 |
※平均勤務時間:9時間30分
勤務時間は10時間前後になることが多く、利用者や職員と頻繁にコミュニケーションを取ったり、膨大な事務作業をこなしたりしなければなりません。
職員の指導・育成のほか、関係機関との連携・調整のために施設外で仕事をすることもあります。
サービス管理責任者は業務量が多く、責任も大きい職種です。
しかし、利用者の成長を間近で感じることができ、非常にやりがいのある仕事だといえるでしょう。
サービス管理責任者に向いている人の特徴は?
サービス管理責任者に向いているのは、以下の特徴を持つ人です。
- コミュニケーション能力
- リーダーシップ
- 注意力
- 責任感
- 事務処理能力
- 営業力
サービス管理責任者は、個別支援計画書の作成のために利用者と面談を行ったり、職員への指導・サポートをしたりします。
自治体や関係機関へ連絡をするだけでなく、ときには利用者に代わって交渉することもサービス管理責任者の業務のうちです。
このように利用者を含めて多くの人と関わるため、高いコミュニケーション能力を持っている人に向いています。
支援員をまとめて円滑に働いていけるような体制と関係を構築するリーダーシップも必要です。
また、
- トラブルが起きないように常に配慮を怠らない注意力と責任感
- 万一の事態が発生した時の対応力
- 多くの書類をさばける事務処理能力
- 新規利用者を獲得する営業力
など、複数のビジネススキルに長けた「ゼネラリスト」タイプの人に適性があります。
何よりも人と関わることが好きで、誰かの役に立つことに喜びを感じられるという人ほどサービス管理責任者に向いているといえるでしょう。
支援が必要な人たちの力になりたいと考えているなら、ぜひサービス管理責任者を目指してみてはいかがでしょうか。
サービス管理責任者の求人状況
サービス管理責任者は需要が高い職業でありながら、長期間の実務経験を要するなど取得要件が厳しく、絶対数が不足しているのが現状です。
2023(令和5)年2月に厚生労働省が公表した資料によると、サービス管理責任者の質と人員を確保できるよう実務経験の緩和を求める要望に応じた研修体系を見直す案も出されています。
しかし、2023年4月時点では、具体的な改正時期などは未定です。
ここ数年でサービス管理責任者等研修修了者数が増えてきているとはいえ、採用競争を緩和するまでには至っておらず、多くの施設が人材確保に苦労しています。
利用者数と事業所数が増加している就労継続支援B型事業所においても、収益の向上と事業の安定性を図るためにはサービス管理責任者を配置することが不可欠です。
障害福祉サービスの開業支援を行っているミライクスでは、就労継続支援B型実践講座を開催しています。
ミライクスには採用に関するノウハウもあり、サービス管理責任者をしっかり確保できるようなアドバイスも受けられます。
また、セミナーを通じて経営者同士のつながりができるのも本講座の魅力です。
障害福祉サービスの開業にご興味がありましたら、まずはミライクスの無料セミナーへお申し込みください。
- 「障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について」(厚生労働省)
- 「自立生活援助の運営ガイドブック」(厚生労働省)
- 「就労定着支援事業所」(独立行政法人福祉医療機構)
- 「サービス管理責任者等研修制度について」(厚生労働省)
- 「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要」(厚生労働省)