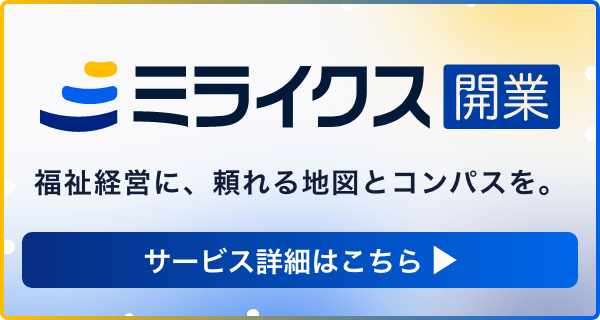事業を準備する
2023.1.21
2023.2.3
グループホームのレクリエーションは何がよい?種類・簡単な例を紹介

グループホームでのレクリエーションは、利用者の気分転換や楽しみのために行うものだけでなく、認知機能や身体機能の維持、心の安定につながるものが実施されています。
レクリエーションの内容は、身体を動かしたり声を出したりするものや、脳トレのようなもの、寝たきりのままでできるものなどさまざまです。
また、障害のある方を対象としたグループホーム(共同生活援助)においても、レクリエーションが行われる場合があります。
この記事ではグループホームで行われるレクリエーションの目的や効果、目的別のレクリエーション例などについて解説します。ぜひ最後までお読みください。
目次
グループホームのレクリエーションとは?

グループホームとは、認知症の高齢者または障害者が専門スタッフの支援のもとで、少人数で共同生活を送る施設です。
グループホームで行われるレクリエーションは、自由時間の余暇活動というよりも、福祉サービスの一環として行われる活動を指しています。
利用者に楽しさを感じてもらう時間であることはもちろん、身体機能の維持や脳機能の活性化、他の入居者とのコミュニケーションなど、さまざまな役割があります。
まずは、認知症高齢者向けのグループホームで行われるレクリエーションについて見ていきましょう。
グループホームにおけるレクリエーションの目的
グループホームで行うレクリエーションは、次の3つの目的で行われます。
- 認知症の進行予防
- 日常生活動作(ADL)の維持・向上
- 生活の質(QOL)の維持・向上
1.認知症の進行予防
認知症の高齢者が暮らすグループホームでは、認知症ケアが欠かせません。
頭を使うゲームをしたり、体操などで身体を動かしたりして、脳機能や身体機能を活性化し、認知症の進行を和らげます。
2.日常生活動作(ADL)の維持・向上
できるだけ自立した生活を送るためには、日常生活動作(ADL=Activiities of Dairy Living)の維持・向上が重要です。
日常生活動作は日常生活に最低限必要な動作を指し、姿勢を変える動作(起居動作)をはじめ、移乗、移動、食事、更衣、排泄、入浴などがあります。
グループホームでは、日常生活動作を維持・向上するためのレクリエーションも取り入れられています。
3.生活の質(QOL)の維持・向上
認知症になり、今までできたことができなくなると、生活の質=QOL(Quality of life)は低下します。
グループホームでは、レクリエーションを通じて身体を動かしたり人とのつながりを持ったりすることで、生活の質の維持・向上を目指します
グループホームにおけるレクリエーションの効果
グループホームのレクリエーションには、次にあげた3つの効果を期待できます。
- 身体機能の維持
- 脳機能の活性化
- コミュニケーションの促進
1.身体機能の維持
認知症により意欲や関心が低下し、身体を動かすことが億劫になると、身体機能が徐々に低下してしまいます。
レクリエーションで定期的に身体を動かすことで、身体機能を維持し、寝たきりを予防します。
2.脳機能の活性化
多くのグループホームで取り入れられている脳トレやクイズは、脳の血流を促し、認知機能の低下を防ぐといわれています。
また、手指を動かして何かを作ったり書いたりするレクリエーションも脳機能の活性化に効果的です。
3.コミュニケーションの促進
レクリエーションは、他の利用者やスタッフとコミュニケーションを深める第一歩です。
外出が億劫だったり、引きこもりがちだったりしても、レクリエーションに参加することで、他の利用者やスタッフとの交流が生まれやすくなります。
グループホームにおけるレクリエーションの頻度
グループホームでのレクリエーションは、原則として自由参加となっています。
毎日行っているところもあれば、月に何回と決まっているところもあり、施設によってさまざまです。
グループホームのレクリエーションの種類は?

グループホームで行われるレクリエーションには以下の3種類があります。
- 集団レクリエーション
- 個別レクリエーション
- 基礎生活レクリエーション
何人かでグループを作り、一緒に同じレクリエーションを行います。
他の利用者やスタッフとの交流には、認知機能の低下防止という効果があるといわれます。
また、レクリエーションに参加して顔見知りが増えれば、引きこもりの解消に繋がり、日々の生活の活力となると考えられます。
認知症の人は、大勢の人と関わるのが難しい場合があります。
他者とコミュニケーションをとることが苦手な人や、認知症の進行により移動が難しい人もいます。
そういった人には、1人または少人数でレクリエーションを行います。
レクリエーションとして決まった時間や場所を決めるのではなく、ふだんの生活の中に身体や脳を刺激するようなレクリエーションの要素を取り入れるものです。
たとえば、室内に花を飾る、食事の際に音楽を流すといったことが当てはまります。
グループホームのレクリエーションの例は?
グループホームのレクリエーションの内容は大きく4タイプに分かれます。
それぞれのタイプについて、目的や具体例を紹介します。
1.身体を使うレクリエーション
身体を動かす運動系のレクリエーションです。
<目的>
楽しみながら身体を動かし、身体機能の維持・向上を目指します。
寝たきりの予防にもつながります。
座ったままでもできるような内容にアレンジすることも可能です。
<身体を使うレクリエーションの例>
- バレー
- ボール運び
- 音楽に合わせて体を動かす
- 体操
- 外出・散歩
- ボーリング
- 玉入れ
- ダンス
- ストレッチ
- 輪投げ
2.頭を使うレクリエーション
脳を刺激する脳トレ系のレクリエーションです。
<目的>
考えたり判断したりすることで、脳の活性化や認知機能の維持を目指します。
<頭を使うレクリエーションの例>
- ゲーム
- パズル
- しりとり
- カードゲーム
- ボードゲーム
- 囲碁・将棋
- そろばん
- 間違い探し
- なぞなぞ
- 計算
3.手先を使うレクリエーション
指先を使う創作系のレクリエーションです。
<目的>
手指を使うことで、脳の働きを活性化させます。
<手先を使うレクリエーションの例>
- 工作
- 絵画
- 手芸
- 料理
- 折り紙
- 手遊び
- 指遊び
- 塗り絵
4.心を安定させるレクリエーション
歌や音楽など、心を穏やかにするレクリエーションです。
<目的>
毎日の生活に不安やストレスを感じている人に、心を落ち着かせてもらうレクリエーションです。
心地よい香りをかいでもらったり懐かしい音楽を聴いてもらうことで、心が安らいだり気持ちがリフレッシュします。
<心を安定させるレクリエーションの例>
- ハンドマッサージ
- アロマテラピー
- 合唱、楽器演奏
- 音楽鑑賞
5.その他のレクリエーション
ほかにも次のようなレクリエーションがあります。
参加者の状態に合わせて行いましょう。
- 回想法
-
昔の写真などを見ながら、思い出を話してもらいます。
昔のことを思い出すことが脳の活性化につながるほか、話を聞いてあげることで利用者の自己肯定感も高まるといわれています。
- 料理、掃除、洗濯などの家事
-
家事をする際は、身体や手先を動かすので、身体機能の維持や脳の活性化を期待できます。
さらに、家事を通して誰かの役に立つという達成感も感じてもらえます。
- 動植物の世話
-
動物や植物に触れ、世話をすることには、心を穏やかにする効果があるといわれています。
アニマルセラピーや園芸療法を取り入れるグループホームが増えているのはこのためです。
重度の認知症の人向けのレクリエーションは?

認知症が進み、ベッドの上で過ごす時間が多くなってくると、参加できないレクリエーションも増えてきます。
しかし、身体機能や脳機能の維持といったメリットを考えると、無理のない範囲で、レクリエーションへの参加を促したいものです。
また認知症のタイプによっては、不安感や孤独感を感じやすい人、意欲が低下している人、身体に麻痺やこわばりがあり思うように動けない人や転倒しやすい人などがいます。
これらも考慮した上で、レクリエーションの内容を決めましょう。
座位が保てる人におすすめのレクリエーション
座ってできるレクリエーションには、以下のようなものがあります。
- 歌を歌う
好きな歌手やジャンルの歌、懐かしい歌などを歌いましょう。
歌は心肺機能の活性化にもつながるといわれます。
- 散歩に出かける
散歩もレクリエーションのひとつです。
車椅子で散歩に出かけてみましょう。
- 絵を描く、折り紙などの手作業をする
- 座位が保てる人なら、テーブルの上で絵を描いたり、折り紙などの手作業をするのもよいでしょう。
- レクリエーションを見学する
- 参加が難しい人でも、レクリエーションを見学し、他の利用者の笑顔を見たり笑い声を聞いたりするだけで、元気になれることがあります。
寝たきりの人におすすめのレクリエーション
寝たきり状態であっても、以下のようなレクリエーションは行えます。
- アロマオイルでハンドマッサージやフットマッサージ
- 心地よい香りのアロマオイルを使い、手や足をやさしくマッサージをしましょう。
- 読み聞かせ
- 短めのエッセイ、新聞、絵本など、好きなものを読んであげるとよいでしょう。
- 映画やスポーツなどの動画鑑賞
- 映画やスポーツが好きな人なら、好きなジャンルの動画を見て楽しんでもらいましょう。
- お化粧をする
- 女性の場合、メイクをしたりマニキュアを塗ってみると、気持ちが前向きになるものです。
- 身体に触れる
身体に触れると、幸せを感じるオキシトシンというホルモンが分泌されるといいます。
背中などをゆっくりさすってあげましょう。
グループホームのレクリエーションの進め方は?

グループホームでレクリエーションを行う際は、準備から片付けまで以下のような流れで行います。
- レクリエーション内容を考える
- レクリエーションの準備を行う
- レクリエーションを実施する
- 会場の片付けを行う
1.レクリエーション内容を考える
認知症の進行度が同じ程度の人でグループ分けをし、参加者の体力や性格、趣味・嗜好の情報を集めておきます。
参加者全員が楽しめそうなレクリエーションを考えます。
参加者の認知症の進行度によっては、ルールが複雑すぎないものを用意するとよいでしょう。
ただし、新しいレクリエーションを考えたり、実施するのは意外と難しいもの。
日頃からインターネットや雑誌をチェックしてアイデアをストックしたり、介護レクリエーションの分野で発信を行っている人のSNSなどを見て、その活動をヒントにしてみましょう。
2.レクリエーションの準備を行う
レクリエーション前日までに以下の準備を行っておきましょう。
(1)材料や道具を準備する
レクリエーションに必要な材料や道具を準備します。
道具が必要な場合は事前に使い方の確認などを行います。
万一の破損などに備えて、道具類は少し多めに準備しておくとよいでしょう。
(2)シミュレーションを行う
利用者やスタッフが座る位置や、全体の流れを決めて、開始から終了まで、頭の中で一通り流れを確認してみましょう。
スタッフにも一緒にシミュレーションしてもらうと、自分一人では気付かなかったよりよいアイデアを得られることもあります。
シミュレーションの結果をふまえ、必要があれば内容を見直したり、材料・道具類を追加で用意します。
3.レクリエーションを実施する
緊張せずリラックスして参加してもらえるよう、スタッフの明るい挨拶から始めます。
場の緊張感をほぐすため、穏やかな雰囲気の曲をBGMに流したり、冒頭にアイスブレイクとして自己紹介や手遊び、スキンシップなどを行うのもよいでしょう。
レクリエーションのルール説明は、ゆっくり丁寧に行います。
利用者の表情もよく見て、不安そうな人がいれば、改めて説明してあげてください。
ルールを説明する際に、スタッフがお手本を見せたり、何人かの参加者に実際にやってもらったりすると、より伝わりやすいでしょう。
スタッフがわざと失敗して笑いを誘うなど、和やかな雰囲気作りを心がけるのもポイントです。
参加者には、積極的な人もいれば、そうではない人もいます。
実施中は全体の雰囲気をよく観察し、参加者の様子を見ながら声かけを行いましょう。
4.会場の片付けを行う
レクリエーションが終わったら、道具や椅子などを片付けます。
次回のために用意したほうがよいものがあれば、忘れないように記録に残しておきましょう。
また、利用者が楽しそうにしていたポイントや、不便そうにしていたことがあれば、話を聞いて改善につなげるとよいでしょう。
グループホームのレクリエーションを盛り上げるポイントは?

グループホームで実施するレクリエーションは、身体機能の維持などを目的に行うものなので、盛り上がることが一番の目的ではありません。
しかしながら、せっかく参加してもらうなら利用者に楽しいと感じてもらいたいものです。
そこで利用者に楽しんでもらうためのポイント3点をご紹介します。
スタッフも利用者も楽しいと感じるレクリエーションの参考にしてください。
自分から楽しむ
利用者に楽しんでもらうには、自分をはじめスタッフが楽しんでいることが大切になります。
初めて司会を任された場合などは、進行させることに精一杯で楽しむことまで気が回らないかもしれません。
そんな時は、盛り上げ上手なスタッフのやり方を参考にするのもよいでしょう。
レクリエーションが毎回同じような内容で、マンネリ化が気になるという人もいるでしょう。
しかし、レクリエーションのたびに新しいことをする必要はありません。
最初の挨拶や、BGM、アイスブレイク、締めくくりの挨拶などは、常に新しいものをと考えず、お決まりのパターンを作ってもよいのです。
「またいつもの楽しい時間が始まった」と感じてもらえるでしょう。
積極的に声かけをする
ルールを理解できているか、楽しんでもらえているかなど、利用者の様子をつぶさに観察しながら、小まめに声をかけましょう。
ただし、子どもにするような言葉遣いで声をかけると、人によっては不快に感じてしまうこともあります。
人生の先輩として敬意を払い、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
全員を褒める
利用者の中にはルールが難しい、上手にできないと感じている人がいるかもしれません。
「みんなと同じように楽しめない」と、自信を無くすこともあります。
「上手にできましたね」「体がよく動いていますね」「お手本にさせてくださいね」など、よいところを見つけて声をかけるようにしましょう。
グループホームでレクリエーションを行う際の注意点は?

グループホームでレクリエーションを行う際は、以下の点に注意することも大切です。
ほどよい難易度設定にする
まず注意したいのは、レクリエーションの難易度です。
難易度が低すぎると、参加者のプライドを傷つけてしまうかもしれません。
「こんな簡単なことをやらせるなんて、馬鹿にしているのか?」「どうしてこんな幼稚なことをしなければいけないの?」と感じられるためです。
ほどよい難易度で、達成感を得られるものがよいでしょう。
安全性を確保する
レクリエーションの際は、何よりも参加者の安全が大切です。
特に身体を使うレクリエーションや道具を使うレクリエーションの時は、事故が起こらないように細心の注意を払う必要があります。
参加者から目を離さず、何かあったら瞬時に対応できるよう心掛けましょう。
無理に参加させない
レクリエーションの内容を苦手に感じる人や、面白さを感じないという人がいるかもしれません。
その気持ちも否定せず、参加を強制しないようにしましょう。
また、レクリエーションの途中で、関係のない話を始めたり、大声を出す人が出てくることもあります。
話をさえぎって無理にレクリエーションに参加させるのではなく、いったん話を聞くなどして、感情が落ち着くまで様子を見るのがよいでしょう。
時間設定に配慮する
レクリエーションの時間が長いと、脳が疲れてしまい、集中力を維持するのが難しくなる場合があります。
特に認知症の人は、強いストレスがかかると周辺症状が強くなるようです。
参加者が飽きてきた、イライラしてきたと感じられたら、休憩時間を設けたり、他のゲームに切り替えたりして柔軟に対応しましょう。障害者グループホームのレクリエーションは?

ここまで認知症高齢者向けのグループホームについて説明してきましたが、「グループホーム」には障害者が支援を受けながら共同生活を送る施設(共同生活援助)もあります。
中でも昼夜を問わず24時間支援体制を確保する「日中サービス支援型」の障害者グループホームでは、高齢者向けグループホームと同様にレクリエーションを行っているところがあります。
障害者グループホームでは、障害の内容や程度に応じ、皆で楽しめるレクリエーションが行われています。
- お正月やクリスマスなどの季節の行事
- 部屋の飾り付けをしたり、外出をして、季節の行事を楽しみます。
- 運動や体操
- 運動機能の低下を防ぐため、身体を動かすレクリエーションが行われます。
- 手指を使った遊び
- 脳機能の活性化に役立つ、手指を使った遊びやゲームなどが行われます。
「どんなレクリエーションが行われているか、実際に見てみたい」という人は、見学可能な障害者グループホームに足を運び、レクリエーションを見学するのもよいでしょう。
障害福祉分野の開業支援を行うミライクスでは、障害者グループホームの開業支援サービス「グループホーム実践講座」を開催しています。
およそ6ヶ月間の研修を通して、グループホームを効率的に経営していくための開業準備を行います。
期間中、講師が運営する施設の見学も可能で、施設によってはレクリエーションの様子なども実際に見ていただくことができます。
障害者グループホームの開業や、レクリエーションなども含めた開業後の運営について、直接講師に質問をしながら、学びを深められる絶好の機会になるでしょう。
ご興味がある方はまずは無料セミナーにお越しください。