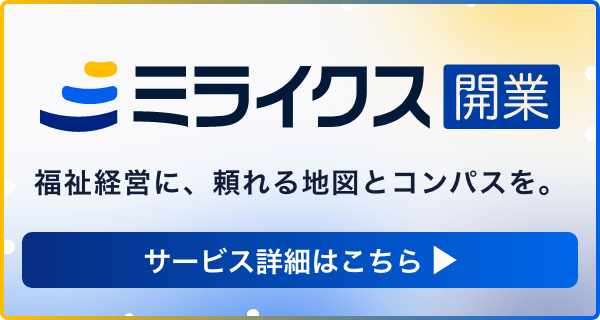事業を準備する
2023.1.22
2023.4.6
職業指導員とは?業務内容・給料・仕事のキツさ・やりがいなどを調査

就職のサポートを通じて社会貢献できるのが、仕事の魅力だといわれています。
しかし「職業指導員になるには何か資格が必要なのでは?」「仕事がキツイのでは?」と気になる人もいるのではないでしょうか。
この記事では、職業指導員の業務内容や1日のスケジュール・給料の目安、就労支援員・生活支援員との違いについて解説します。
職業指導員の仕事のやりがい・キツさに関するアンケート結果も紹介するので、職業指導員になりたいと考えている人はぜひ参考にしてください。
目次
職業指導員とは?

職業指導員とは障害者や難病にかかっている人を対象に、一般企業で働くために必要なスキル・技術やマナーを身に付けるための支援を行う職種です。
就労継続支援A型・B型事業所や就労移行支援事業所が主な職場ですが、障害者支援施設や短期入所(ショートステイ)で働く職業指導員もみられます。
本人の希望・能力はもちろん、心理面や障害・疾病の特性を考えながら個別に支援する場面も多いのが特徴です。
人柄やこれまでの職歴で積み上げたスキルを活かして、障害者や難病患者が地域で自立した生活を送れるように支援することで社会貢献にもつながります。
また、児童養護施設・児童自立支援施設では実習・研修といった職業訓練や職業に関する情報提供を通じて、児童が希望する仕事に就くためのサポートを行います。
施設を退所した児童へのアフターケアも担当業務となっており、社会人としてスムーズに自立できるよう長い目で支援していきます。

職業指導員と生活支援員の違い
職業指導員は一般企業への就職を実現できるように障害者・難病患者や児童を支援するのに対し、生活支援員は障害者の日常生活をサポートしています。
グループホームなどの入所型施設では職業相談に対応する場面もあり、職業指導員と似た一面もみられます。
ただし、就労継続支援B型のような通所型の事業所では、食事や排せつといった利用者のケアが主な業務です。
▼職業指導員と生活支援員の違い
| 職業指導員 | 生活支援員 | |
|---|---|---|
| 支援対象 | ・一般企業への就職を希望する障害者や指定難病の患者 ・児童養護施設・児童自立支援施設・福祉型障害児入所施設に入所している児童 |
・就労継続支援B型や生活介護事業所などに通っている障害者・指定難病の患者 ・障害者支援施設やグループホームに入所している障害者 ・ショートステイを利用する障害者 |
| 支援内容 | ・一般企業で働くために必要なスキル・技術やマナーの指導 ・児童に対しては、職業訓練の実施や職業選択に関する情報提供 |
・食事や排せつなど日常生活の支援 ・日常生活に関する相談対応 ・創作活動や生産活動といった日中活動の支援 ・職業相談や就労支援に関与することもある |
就労継続支援B型と生活介護を併設する事業所のように、複数の障害福祉サービスを提供する多機能型事業所では、人員配置の兼ね合いから職業指導員が生活支援員を兼務する場合もあります。
また、利用者が多い時間帯に管理者が職業指導員または生活支援員を兼務している事業所もみられます。
職業指導員と就労支援員との違い
職業指導員は就職するために必要とされる技術面の指導を行うのに対し、就労支援員は求人に応募する支援や就職後のフォローアップを主に担当します。
就労支援員は就労移行支援などの就労系障害福祉サービス事業所だけでなく、自治体に設置された福祉事務所や保健福祉関係の部署でも勤務しています。
▼職業指導員と就労支援員の違い
| 職業指導員 | 就労支援員 | |
|---|---|---|
| 支援対象 | ・一般企業への就職を希望する障害者や指定難病の患者 ・児童養護施設・児童自立支援施設・福祉型障害児入所施設に入所している児童 |
・一般企業への就職を希望する障害者や指定難病の患者 ・生活保護の受給者 ・住居確保給付金を受給するなど生活が苦しい人 ・ひとり親の母親・父親 |
| 支援内容 | ・一般企業で働くために必要なスキル・技術やマナーの指導 ・児童に対しては、職業訓練の実施や職業選択に関する情報提供 |
・就職活動を進める支援 ・職場実習先や求人先の開拓 ・就職後のフォローアップ |
就労継続支援B型事業所には就労支援員の配置が求められていませんが、職業指導員として就職活動のサポートに携わるなど、就労支援員としての役割を果たす場面もみられます。
しかし、自治体に勤務する就労支援員は地方公務員法で副業が制限されている関係で、他の事業所の就労支援員と兼務することはありません。
職業指導員の仕事内容はどんなもの?

職業指導員の具体的な仕事内容は勤務先によって異なりますが、就労系障害福祉サービス事業所で働く人が大半です。
厚生労働省の調査によると、職業指導員の常勤換算従事者数は約4万1,000人、そのうち約65%の2万7,236人が就労継続支援B型で働いていることがわかります(※)。
常勤換算とは事業所で働いている職員の平均人数のことで「職員の勤務のべ時間数÷常勤職員の所定労働時間」という式で算出されます。
例えば、週20時間働く非常勤の職業指導員が2人いれば、常勤(週40時間勤務)の職業指導員1人としてカウントするという考え方です。
したがって、実際には職業指導員が2万7,236人より多くなる点を理解しておきましょう。
統計には出ていませんが、児童養護施設や児童自立支援施設・福祉型障害児入所施設といった児童福祉施設で職業指導員として働く人もみられます。
続いて、職業指導員の仕事内容を勤務先ごとに紹介します。
※出典:「令和2年社会福祉施設等調査の概況 結果の概要 2 障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の状況」(厚生労働省)
就労継続支援B型
就労継続支援B型とは、一般企業への就職が難しい障害者に生産活動の場を提供する事業所です。
雇用契約を結ばないため、利用者は障害・疾病の特性や体調などに合わせて柔軟に働けます。
就労継続支援B型事業所の職業指導員は事業所が取り扱う商品・サービスの内容に応じて、作業手順や生産活動に必要な知識・技術を具体的に指導します。
利用者の希望や適性に応じて、働く能力を引き出すことを前提に支援しているのが特徴です。
事業所によっては、一般企業の求人に応募するためのサポートを行う場合もあります。

就労継続支援A型
就労継続支援A型とは、一般企業で働くのは難しいものの決められたルールに従って働ける障害者に生産活動の場を提供する事業所です。
利用者は雇用契約を結んで、一般企業の従業員と同様のスタイルで働きますが、障害・疾病の特性や体調に応じて個別の配慮を受けられます。
事業所によっては、雇用契約を結ばずに利用できる場合もあります。
就労継続支援A型事業所の職業指導員も、生産活動に必要な知識・技術を具体的に指導します。
雇用契約がある関係で、上司役として利用者をマネジメントする場面もみられるのが特徴です。
一般企業に就職できる可能性を見越した支援を行っているといえます。
就労移行支援
就労移行支援とは、障害者が一般企業の求人に応募して就職を実現するために必要な支援を提供する事業所です。
事業所内では、コミュニケーション能力や集中力・体力の向上を目指すトレーニングを実施します。
さらに、職場環境のイメージづくりを目的に外部での職場実習も行います。
応募書類の作成支援や模擬面接を実施したり、応募先の面接に同行したりするなど、転職エージェントに似た機能を持つのも特徴です。
就労移行支援事業所の職業指導員は、事業所内でのトレーニングや就職活動の支援を担当します。
利用者の希望・特性に合った職場を探すために、就労支援員と連携して仕事を進める場面も多く見られます。
短期入所
短期入所(ショートステイ)とは病気などで家族の介護が難しくなった時に、障害者を一時的に障害者支援施設または児童福祉施設に入所させることができるサービスです。
家族が休息したい時も利用できるので、レスパイトケアとしての役割も持っています。
食事や入浴・排せつなど日常生活の支援やレクリエーション活動を実施します。
短期入所では利用者のケアを主な目的としているため、職業指導員の配置義務はありません。
しかし、生活相談の一環として入所先に所属する職業指導員が就労に関する相談に対応する場合があります。
利用者の希望に応じて、就労継続支援A型・B型事業所の利用につなげる場面もみられます。
児童福祉施設
児童福祉施設とは、生活・学習の指導や家庭環境の調整を通じて子どもの健全な成長を支援する施設です。
職業指導員は、実習設備を設けて職業指導を行う児童養護施設・児童自立支援施設や福祉型障害児入所施設に配置されています。
児童福祉施設の職業指導員は、実習や講座などを通じて職業に関連する知識・技術の教育を行います。
厚生労働省の通知では学校教育や塾・習い事では得られない内容を前提としているため、専門性が高いのが特徴です。
子どもが希望する仕事を選ぶために必要な情報提供や相談・助言だけでなく、就職後のアフターフォローも行います。
なお、児童福祉施設で働く職業指導員は少数だといわれています。
職業指導員の仕事はキツイ?

職業に関する指導を通じて障害者等に向き合える仕事に魅力を感じる一方で、中には職業指導員の仕事はキツイのでは?と気になる人もいるようです。
ここでは、職業指導員の経験者へのアンケート調査結果をもとに、仕事がキツイと感じる場面ややりがいを感じる場面、職業指導員に必要な心がまえにフォーカスを当てて解説します。
実施時期:2022年11月
調査概要:職業指導員として働いたことのある方へのアンケート
調査対象:職業指導員として勤務したことのある方(10名)
調査媒体:クラウドワークス
職業指導員の仕事のキツさ
アンケートに回答した人10名のうち7名が、職業指導員の仕事はキツくないと答えました。
職業指導員の仕事がキツくないと思う理由として、次のようなコメントがありました。
就労移行支援事業所に通ってくださる方々は、障害が比較的軽く、真面目で素直な方が比較的多いため、指導がしやすいためです。いきなり暴れたり大声を出す方もいなく、体力的にも楽でした。(40代男性)
給料は高くはありませんでしたが特別低くもないことと、残業もほとんどなく働きやすい環境でした。また、障害者の方々が素直でこちらが教えたことに対して答えてくれて結果になる事も多くやりがいもあったので、あまりキツいと思ったことはありませんでした。(30代女性)
人とのコミュニケーションを通じて相手の気持ちを思いやることがなによりもやりがいに感じるため、きついと思ったことはなかったです。また、普段から冷静な判断能力と分析をする癖があるので、それもきついと思わない理由の一つです(20代女性)
利用者様が少ない事業所だったので、他職員含め和気あいあいと訓練が出来ていました。体調を崩しやすい方もいらっしゃいましたが、焦らずゆっくりを第一前提として話を聞いていく中で信頼関係を築く事もできたので、キツイと思ったことはなかったです。(30代女性)
一方、利用者の対応や職業指導・個別対応の準備にキツさを感じている職業指導員がいるのも実情です。
職業指導員の仕事がキツイと思う理由についてのコメントも紹介します。
障害者の職業に関する指導のために、こちらも指導に必要な技能をある程度は身に着ける必要があるのが大変でした。また、ぞれぞれの障害者に応じた指導も求められました。それだけでなく、事業所側としての職員としての仕事もあったので、一か所でダブルワークをしている感じだったです。(30代女性)
遣り甲斐をもって取り組むが、利用者が作業に取り組みやすい環境づくりや前準備、作業中の指導、個別に対応しつつトラブルにもすぐに対応しなければならないなど。一般企業で働くよりも負荷が大きい。(40代女性)
利用者の方の感情のコントロールをサポートしたりするので、職員側は常に万全の精神状態で、何が起こっても冷静に対応できる心構えでいないと、利用者の方の突発的な行動や発言に対処しきれずに、自分自身が精神的にまいってしまうことがあります。(30代女性)
事業所の環境や利用者像によって、仕事のキツさが変わるといえるでしょう。
職業指導員の給料
厚生労働省の調査によると、令和3年9月時点での職業指導員の給料は以下のとおりでした。
処遇改善加算制度の効果もあり、賃上げ率は一般企業(1.86%)を上回っています。
▼常勤の給与
| 令和3年9月 | 令和2年9月 | 賃上げ率 | |
|---|---|---|---|
| 特定処遇改善加算あり | 288,730円 | 276,250円 | 4.5% |
| 処遇改善加算あり | 274,450円 | 262,540円 | 4.5% |
| 処遇改善加算なし | 273,920円 | 261,480円 | 4.7% |
▼非常勤の給与
| 令和3年9月 | 令和2年9月 | 賃上げ率 | |
|---|---|---|---|
| 特定処遇改善加算あり | 117,270円 | 105,880円 | 10.7% |
| 処遇改善加算あり | 108,240円 | 101,210円 | 6.9% |
| 処遇改善加算なし | 105,680円 | 98,790円 | 7.0% |
※平均給与額は、基本給+手当+一時金(10〜3月支給金額の1/6)により算出。また、10円未満を四捨五入している。
ちなみに処遇改善加算とは、職業指導員など特定の職種の給与を増やす資金を確保できるよう、一定の条件を満たす障害福祉サービス事業所の報酬を加算する制度です。
昇給制度だけでなく研修制度・職場環境などの充実度に応じて加算割合が変わります。
また、経験・技能の高い介護福祉職の待遇改善を目的とした「特定処遇改善加算」制度も2019年からスタートしています。
仕事の成果が給与に反映される可能性があるのも、職業指導員の魅力の一つといえるでしょう。
出典:「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(厚生労働省)
職業指導員の1日のスケジュール
就労継続支援A型・B型事業所での、職業指導員の1日のスケジュール例を紹介します。
事業所のサービス提供時間帯や勤務体系によって始業時刻・終業時刻は異なりますが、どのような流れで仕事を進めるのかをイメージしてみてください。
▼就労継続支援A型・B型事業所での1日のスケジュール例
| 時間 | スケジュール | 主な仕事内容 |
|---|---|---|
| 8:00 | 出勤 | 1日のスケジュール確認や利用者からの連絡対応 |
| 8:15 | 朝のミーティング | 職員と業務内容や連絡事項などを共有 |
| 8:30 | 送迎※ | 事業所の車両で利用者を迎えに行く |
| 9:00 | 朝の会 | 利用者の体調確認・作業の分担・当番の確認など |
| 9:15 | 午前の作業 (作業途中に1~2回休憩あり) |
・利用者の介助や作業指導、当番活動の支援 ・事業所で食事を提供する場合は調理に携わることもある |
| 12:00 | 昼休み | ・昼食をとる ・利用者の介助を行う場合は昼休みの時間を調整する |
| 13:00 | 午後の作業 (作業途中に休憩する場合もあり) |
利用者の介助や作業指導、当番活動の支援 |
| 15:00 | 帰りの会 | ・利用者とその日の作業を振り返る ・事業所内の清掃・帰りの支度 |
| 15:15 | 送迎※ | 事業所の車両で利用者を送り届ける |
| 16:00 | 事務作業 | ・業務日誌・支援記録の作成 ・翌日の送迎ルートづくり ・スタッフ間の情報共有 |
| 17:00 | 退勤 |
※送迎は利用者の自宅が基本だが、キーパーソンと合意した特定の場所に送迎することもある
上記の他に、以下の仕事に携わる場面もあります。
- サービス担当者会議への出席
- 家族などキーパーソンとの面談
- 事業所内研修への参加
- レセプトの作成
また、将来的に一般企業へ就業するためのイメージづくりなどを目的として、通常の作業の代わりに外部施設などの見学や事業所内での調理実習を取り入れる事業所もみられます。
ただし、通常の作業以外のプログラムを実施する際は、就労支援の一環として取り組む旨をあらかじめ個別支援計画に明記する必要があるのでご注意ください。
職業指導員のやりがい
職業指導員へのアンケート調査結果では、以下のような場面で仕事のやりがいを感じると回答がありました。
- できる作業が増えるなど進歩がみられた時
- 利用者の夢や希望に寄り添い、実現に向けて一緒に考えている時
- 利用者や家族から笑顔が出た時
- 就労継続支援A型事業所への移行などステップアップが実現した時
具体的には以下のようなコメントが寄せられています。
これまでは上手くいかなかった作業が毎日、少しずつの進歩が見られので、そういう時には職業指導員を行っていて良かったと感じました。(30代女性)
徐々に体調、生活リズムが整い、一般的に見れば些細な変化かもしれませんがその方にとっては大きな一歩を踏み出そうとしている時に手助けができ、訓練や面談を重ねる中で目標を見つけ最終的に笑顔で卒業していく利用者様を見ると指導員側のモチベーションも上がりとてもやりがいがあると思います。(30代女性)
訓練を通して、実際に企業の方で働いている姿を見ると、自分の中で達成感もあります。また時には顔を見にいき、話をすることで成長しているなとうれしくなります。就職させていただいた企業様とも縁ができ、また新たに働きたいと思っている利用者を勧めることができ、更に幅が広がる時にやりがいを感じます。(30代男性)
利用者の対応や支援内容の検討に苦心する場面はあるものの、自分で考えた支援計画をもとに職業訓練を行うことで利用者の希望や家族の要望が叶えば大きなやりがいにつながるでしょう。
個別支援を通じて利用者の人生に向き合う場面もあり、支援を続けることで自分自身の成長につながるのも職業指導員の仕事の魅力です。
職業指導員に必要な心がまえ
職業指導員は利用者にとって仕事の手本になる存在で、一般企業に置き換えると上司にあたります。
したがって、職業指導員には利用者や家族と真摯に向き合う姿勢はもちろん、以下のような心がまえが必要です。
- 利用者にとってわかりやすい言葉や動作で指導する
- 利用者の行動や発言に左右されず、的確な判断と指導をする
- 事業所が提供する商品・サービスに関する知識を増やす
- あらゆる角度から利用者への接し方を検討する
利用者の中には、職業指導員をはじめとする事業所のスタッフに依存してしまい、適正な関係性を保てなくなる人も見受けられます。
利用者一人ひとりの思いや障害・病気の特性に寄り添う姿勢は必要ですが、「職員と利用者」という関係性を保った立ち位置で日々の支援に取り組むことが大切です。
職業指導員に向いている人はどんな人?
先ほど紹介したアンケートの結果をもとに、職業指導員に向いている人はどんな人かをまとめてみました。
向上心のある人
利用者と向き合う中で、すぐに支援の成果が出ない場面や個別支援計画どおりに指導が進まない場面は少なくありません。
支援方法を変更したり新たな指導方法にチャレンジしたりする向上心を持ち続けていれば、何らかの形で職業指導の成果が表れるでしょう。
生活支援員や相談支援事業所の職員などの他職種と連携できれば、さらに支援の幅を広げていけます。
臨機応変に対応できる人
利用者へのサービス提供中(職業指導中)は常に体調や感情の変化を観察し、普段と異なる行動・発言があった場合には的確な対応をとる必要があります。
利用者の欠席が多い日には、作業計画の調整も必要です。事業所のルールを守りつつ、許される範囲で柔軟に対応する能力のある人も職業指導員に向いています。
聞き上手であるとともに話し上手な人
利用者の希望に添った支援を行うには、利用者本人だけでなく家族や他事業所の職員からの情報収集が必須です。
その上で、利用者にわかりやすい言葉で生産活動や事業所の利用に関する情報を提供していくことになります。
「共感する」「話を上手にまとめる」といった聞く力と、「はっきり伝える」「聞き手を混乱させない」姿勢で話す力を兼ね揃えていれば、利用者だけでなく関係者と信頼関係を築いて効果的な支援を提供できます。
職業指導員の資格要件は?

職業指導員になるために必須の資格は、法令では特に定められていません。
そのため、介護福祉や職業指導に関する資格や経験がない人でも、仕事への熱意があれば職業指導員を目指せます。
職業指導員は生産活動に関する知識・技術の指導だけでなく、働く姿勢や他人とのコミュニケーションに関する指導を行う場面が少なくありません。
そのため、職歴で得たスキルだけでなく企業で働いたあらゆる経験が職業指導員としての強みとなります。
ただし、事業所によっては質の高いサービスを提供する観点から、社会福祉士や介護福祉士などの保有資格や一定の実務経験を応募要件としている場合もあります。
送迎業務のために普通自動車免許を必須とする事業所も少なくありません。
大規模な事業所で働く場合は、マイクロバスを運転できる中型免許があれば有利かもしれません。
職業指導員になるために有利な資格
職業指導員として働くために、持っていれば有利な資格を5つ紹介します。
個別支援計画の作成やサービスの品質管理を担当するサービス管理責任者になる場合にも有利にはたらくので、ステップアップのために取得を検討してみてもよいでしょう。
なお、就労継続支援A型・B型事業所の管理者になるには社会福祉士・社会福祉主事任用資格・精神保健福祉士のいずれかの資格が必須です。
社会福祉主事任用資格は、厚生労働省が指定する社会福祉関係の科目を3科目以上修了した上で大学や短期大学を卒業した後に得られます。
在籍していた学校に資格証明書を発行してもらえば資格を証明できるので、別途試験を受ける必要はありません。
児童指導員任用資格は、教員免許を取得済の人や4年制大学で社会福祉学・心理学・教育学・社会学のいずれかの学科を卒業した人が得られます。
高卒でも、放課後等デイサービスなどの児童福祉事業で2年以上の実務経験を積めば児童指導員任用資格を得られます。
障害福祉サービス事業所や児童福祉施設が児童指導員として任命した期間に限り、資格の効力が生じるのが特徴です。
社会福祉士とは、福祉に関する相談援助や助言・指導を行う国家資格職です。
社会福祉士になるには一般の4年制大学を卒業後、養成施設の課程を修了した上で社会福祉士国家試験に合格するなど複数のルートが設けられています。
介護福祉士とは、心身に障害がある人の日常生活を支援する国家資格職です。
介護福祉士になるには、介護事業所や障害福祉サービス事業所で3年以上の実務経験を積み、その間に実務者研修を修了してから国家試験に合格するルートが一般的です。
ただし、職業指導員として働いた期間は実務経験にカウントされないのでご注意ください。
精神保健福祉士とは、精神障害者やメンタルヘルス不調者の相談に対応し、社会復帰を支援する国家資格職です。
精神保健福祉士になるには、一般の4年制大学を卒業後、養成施設の課程を修了した上で国家試験に合格するなど複数のルートが設けられています。
職業指導員に役立つ研修
職業指導員として働く場合、介護職員初任者研修を修了しておけば生活支援員と一緒に利用者のケアができ、仕事の幅が広がる可能性があります。
介護職員初任者研修とは、介護職員として働くために必要な基本的な知識・技術を学ぶ研修です。
介護福祉サービスのあらゆる場面で求められる、食事や排せつ・体位の変換や車椅子への移乗といった身体に関する介護技術は実技講習で身につけられます。
調理や洗濯・清掃などの生活支援の技術も、事業所の運営に役立つでしょう。
最近ではオンライン講座も開設されており、休日に実技講習を受けるカリキュラムであれば在職中でも短期間で介護職員初任者研修を修了できます。
なお、訪問介護員(ホームヘルパー)2級の研修を修了していれば、介護職員初任者の修了者として取り扱われます。
職業指導員の求人状況とこれから
障害福祉サービスの利用者は年々増えており、それに伴い事業所数も増加傾向です。
特に、2020年9月時点での就労継続支援B型事業所の利用実人員は35万9,732人で、平成30年9月時点と比べて約6万2,000人(約21%)増えています。
発達障害や行動障害の認知度が高まっていることに加えて、医療機関や自治体の相談体制・情報提供の充実によって障害福祉サービスの利用につながっているものと考えられます。
| 利用実人員 | 事業所数 | |
|---|---|---|
| 2020年9月 | 359,732人 | 13,355事業所 |
| 2019年9月 | 332,487人 | 12,497事業所 |
| 2018年9月 | 297,259人 | 11,835事業所 |
また、独立行政法人福祉医療機構の調査(※)によると、障害福祉サービス事業所の半数が人員不足の状態です。
中でも、7割強の就労系サービス事業所で職業指導員が不足していると認識しています。
就労継続支援A型・B型事業所や就労移行支援事業所では、利用者10名ごとに職業指導員1名以上の配置が人員基準で義務づけられています。
職業指導員の需要は今後も高い状態が続くと考えられ、経営者として円滑に事業所を運営し、利用者の就労機会を確保するためには職業指導員の確保対策が重要です。
※出典:「2020年度障害福祉サービス事業所等の人材確保に関する調査」(独立行政法人福祉医療機構)
ミライクスでは、就労継続支援B型実践講座を受講した方を対象に開業支援サービスを提供しています。
約6ヶ月間の研修を通じて、就労継続支援B型事業所の経営ノウハウ指導はもちろん、職業指導員をはじめとする職員の採用・育成や集客支援も受けられます。
就労継続支援B型事業所の開設にご興味のある方は、一度ご相談ください。