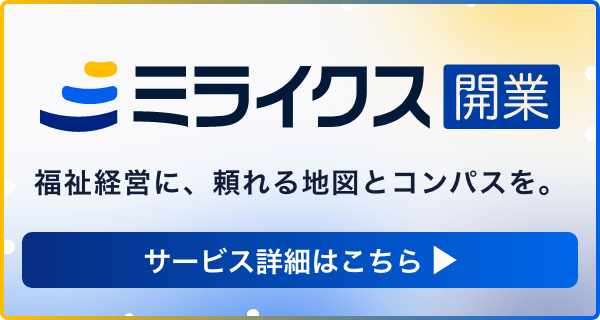事業を探す
2023.5.31
2023.5.29
児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは?対象・役割・指定基準を比較

児童発達支援は未就学児、放課後等デイサービスは原則として18歳までの就学児が利用対象です。
一方、人員配置や設備基準はほぼ共通しているため、多機能型事業として児童発達支援・放課後等デイサービス両方のサービスを提供する事業所もみられます。
この記事では、児童発達支援と放課後等デイサービスの違いについて、利用者の方が気になる役割・支援内容はもちろん、事業者様向けに人員配置・設備基準の面からも詳しく解説します。
目次
児童発達支援と放課後等デイサービスの対象の違いは?

児童発達支援と放課後等デイサービスは、どちらも障害児を支援する通所型のサービスですが、対象となる年齢層は異なります。
▼サービス対象者
| 児童発達支援 | 0歳~6歳までの、未就学の障害児 |
|---|---|
| 放課後等デイサービス | 6歳から18歳までの、以下の学校に通う障害児 ・小学校 ・中学校 ・義務教育学校(小・中一貫校) ・高等学校 ・中等教育学校(中・高一貫校) ・特別支援学校(小学部・中学部・高等部) |
児童発達支援は0歳からでも利用できますが、実際には1歳半健診を受けた後に地域の保健師から子どもの発達に関するアドバイスを受けて、利用を始める人が多いとされています。
また、放課後等デイサービスは利用中に満18歳に達しても、自治体に申請すれば満20歳まで継続して利用することが可能です。
障害児には心身に障害がある子どもだけでなく、発達に特性があるために医師・保健師や児童相談所・市町村の保健センター・子育て支援センターなどから療育が必要だと認められた子どもも含まれます。
したがって、療育手帳・身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳がなくても児童発達支援・放課後等デイサービスを利用できます。
子どもの発達が気になると保護者が気づいて、子育て支援センターなどに「児童発達支援・放課後等デイサービスを利用したい」と相談しても問題ありません。
なお、何らかの理由で高校に進学しなかった障害児は放課後等デイサービスを利用できませんが、障害福祉サービスの生活介護事業所は利用できます。
児童発達支援と放課後等デイサービスの役割・支援内容の違いは?
児童発達支援では保育を基盤とした支援を提供しているのに対し、放課後等デイサービスでは地域社会への参加を視野に入れた支援を提供しているという違いがみられます。
児童福祉法でも、児童発達支援と放課後等デイサービスの役割の違いが明確化されています。
▼児童福祉法で定められた役割
| 児童発達支援 | ・日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与 ・集団生活への適応訓練 |
|---|---|
| 放課後等デイサービス | ・生活能力の向上のために必要な訓練 ・社会との交流の促進 |
一方、
- 障害児の最善の利益を守る役割
- 専門的な知識や経験に基づく支援を通じて障害児の生きる力を引き出す役割
は共通です。
他の事業所や保育施設・教育機関などと連携して支援を進める場面も少なくありません。
地域の自立支援協議会に参加して、自治体や他職種と情報交換を深める事業所もみられます。
障害児への支援を円滑に進めるために、保護者やきょうだいといった家族への支援も実施しています。
また、それぞれの事業所が創意工夫をこらしながら良質な支援を提供していく枠組みとして、厚生労働省から「児童発達支援ガイドライン」と「放課後等デイサービスガイドライン」が公表されています。
それぞれのガイドラインに示されている支援内容を簡単に紹介します。
児童発達支援での支援内容
児童発達支援では障害のある子どもの情緒を安定させ、遊びを通じて表現力・創造力や他人とかかわる力を育む支援を行っています。
厚生労働省の保育所保育指針と同様に、子どもとの信頼関係を築いた上で基本的な生活習慣を整え、家庭や地域社会とかかわりながら健全に成長できるように促しているのが特徴です。
障害児本人への支援内容は以下の5つの領域に分かれていますが、相互に関連しあっています。
1.健康・生活
健康で安全な日常生活や社会生活を送れるよう、身の回りの清潔保持や食事・着替え・排泄といった基本的な生活スキルを身につけるための支援です。
健康状態の観察や発達・障害の度合いに応じたリハビリテーション(機能訓練)も行います。
2.運動・感覚
日常生活の動作の基本となる、姿勢保持や身体の移動能力の向上を目指す支援です。
遊びを通じて視覚・聴覚・触覚などの感覚を活用する支援も行います。
必要に応じて、眼鏡や補聴器などの活用についても支援します。
3.認知・行動
感覚を活用して収集した情報を取捨選択して、具体的な行動につなげる認知機能の発達を促す支援です。
空間・時間などの概念を形成したり、数や形・重さ・色などの違いを認識したりする支援も行います。
こだわりや偏食への支援など、適切な行動を促す対応も行います。
4.言語・コミュニケーション
他人と適切にコミュニケーションを取れるように、話し言葉や文字・記号などを使った意思疎通を促す支援です。
障害や発達の特性に合わせて、手話や点字・やさしい表現といったコミュニケーション手段の活用についても支援します。
5.人間関係・社会性
周囲の人と安定した関係性を構築できるよう、愛着行動(アタッチメント)を形成する支援です。
遊びを通じて、社会性の発達や感情のコントロールを促す支援も行います。
将来の社会生活を視野に入れながら、集団に参加する際の手順やルールの習得についても支援します。
本人への支援に加えて、地域の中で同年代の子どもと仲間作りができるように、保育所や幼稚園・認定こども園・子育て支援拠点と連携して障害児の受け入れ体制を整えるなどの支援も行っています。
なお、重度の障害や日常的な医療的ケアが必要などの事情で外出が難しい子どもが利用できる「居宅訪問型児童発達支援」を提供する事業所もあります。
放課後等デイサービスでの支援内容
放課後等デイサービスでは学校卒業後に社会生活へ移行することを前提に、年齢や発達段階に応じた活動を通じて、大人になるための知識・技能の獲得を促す支援を行っています。
学校の放課後や長期休暇時の支援が主体ですが、土日祝日の利用に対応する事業所や平日の午前中から不登校児を受け入れる事業所もみられます。
放課後等デイサービスは障害児の心身の発達を支援するだけでなく、安全な居場所として機能しているのが特徴です。
仕事・家事との両立支援やレスパイト(休息)の提供という形で、障害児の保護者を支援する一面もみられます。
障害児本人に対する支援は以下の4つの基本活動で構成されており、個別療育・集団療育の形で行われます。
1.自立支援と日常生活の充実のための活動
年齢や発達度合いに応じた遊びを通じて自己肯定感を高め、意欲的な日常生活を送れるように支援する活動です。
自立支援の一環として、支援の方針や役割について学校と打ち合わせながら支援を進めていきます。
ダンス・体操や普段の生活をテーマにしたゲームなど、事業所によって活動プログラムはさまざまです。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)を取り入れる事業所も少なくありません。
2.創作活動
子どもの豊かな感性を育み、表現する喜びを実感できるように支援する活動です。
絵や工作・調理体験などを通じて創造力を引き出していきます。
音楽療法やリトミックを軸にした療育に取り組む事業所もみられます。
3.地域交流の機会の提供
社会見学や地域住民との交流活動を通じて、子どもの社会生活の幅を広げるための活動です。
子どもの心身の状態に配慮しながら、ボランティアの受け入れや地域開放などに取り組んでいます。
同一法人の事業所や近隣の事業所と連携して世代間交流に取り組む事例もみられます。
4.余暇の提供
落ち着いた雰囲気の中で情緒の安定を図りながら、子ども自身が希望する活動を支援します。
学校や家庭とは異なる、第三の居場所を確保する一面があるのも特徴です。
放課後等デイサービスは児童発達支援と異なり、支援対象となる障害児の年齢層が広いです。
進学や思春期による心身の変化が大きいため、通学する学校との情報共有や保護者への相談援助が重要視されています。
また、高校や特別支援学校の高等部の卒業が近づくと、相談支援事業所と連携して生活介護事業所や就労継続支援A型・B型事業所といった障害福祉サービス事業所との連絡調整にも携わります。
児童発達支援と放課後等デイサービスの指定基準の違いは?

それではここからは、児童発達支援や放課後等デイサービスの開業を検討されている方に向けて、指定基準や報酬の加算・減算の要件について見ていきましょう。
児童発達支援と放課後等デイサービスの指定基準はほとんど同じで、報酬の加算・減算の要件も共通です。
ただし、地域の中核施設となる児童発達支援センターについては、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所と異なる基準が定められています。
児童発達支援と放課後等デイサービスの人員配置基準
児童発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所では、児童発達支援管理責任者や児童指導員などの有資格者の配置が必須です。
配置が必要な職種・人数や配置条件・主な仕事内容を紹介します。
▼児童発達支援と放課後等デイサービスの人員配置基準
| 職種 | 必要な人数 | 配置条件 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1人以上 | 管理業務に支障がなければ、児童発達支援管理責任者など他の職務と兼務可能 |
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | 最低でも1人以上は専任かつ常勤 |
| 児童指導員または保育士 | 2名以上 | 最低でも1人以上は常勤 障害児の数が10人までの場合…2人以上 障害児の数が10人を超える場合…障害児5人以内ごとに1人以上を配置 |
| 機能訓練担当職員 | 必要な人数 | 機能訓練の内容に応じて、以下のいずれかの職種を配置 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・心理指導担当職員(臨床心理士・公認心理師) |
| 看護職員 | 必要な人数 | 医療的ケアを行う場合に、以下のいずれかの職種を配置
・保健師 ・助産師 ・看護師 ・准看護師 |
管理者
事業所の運営を統括する仕事です。
管理者として必須の資格要件はありませんが、職員の退職や欠勤に備えて児童発達支援管理責任者または児童指導員の資格を持っていれば安心です。
児童発達支援管理責任者
現場のリーダーとなる職種で、主に児童発達支援計画(個別支援計画)の作成や、サービス提供に関するアセスメントとモニタリングを行います。
児童発達支援管理責任者は他の職種と兼務できません。
児童発達支援管理責任者になるには、以下のいずれかの実務経験に加え、サービス管理責任者等研修(サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修)の基礎研修と実践研修を修了する必要があります。
ただし、基礎研修は実務経験を満たす2年前から受講可能です。
基礎研修の修了後は、2人目以降の児童発達支援管理責任者として個別支援計画の原案を作成できます。
- 相談支援業務の期間が5年以上
- 相談支援業務と直接支援業務の期間を通算して5年以上
- 直接支援業務の期間が8年以上(※)
- 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士など特定の国家資格を保有している場合は、相談支援業務と直接支援業務の期間を通算して3年以上
- 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士など特定の国家資格者としての業務期間が5年以上
※児童指導員・介護職員初任者研修・訪問介護員2級以上の修了者は5年以上
児童指導員または保育士
児童指導員または保育士は、障害児に直接支援を提供する仕事です。
このうち児童指導員には、以下の任用資格が必要となります。
- 教員免許の取得者
- 社会福祉士または精神保健福祉士の有資格者
- 高卒かつ児童福祉事業の実務経験が2年(360日)以上の人
児童指導員の実務要件となる「児童福祉事業」とは、児童福祉法で定められた施設・事業のことをいいます。
- 児童発達支援事業所
- 放課後等デイサービス事業所
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ、学童保育)
- 地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター)
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
ちなみに、最終学歴が中学校卒業の人も、3年以上かつ540日以上児童福祉事業に従事すれば児童指導員の実務要件を満たします。
都道府県知事が適当と認めたものという条件はあるものの、実際には職務経歴書や管理者・施設長などが発行する実務経験証明書で3年以上の従事が確認できれば、都道府県知事の審査を受けなくても児童指導員の任用資格を得られます。
なお、児童発達支援や放課後等デイサービスでは無資格者によるサービス提供が禁止されていません。
将来の児童指導員候補として、あるいは障害児への支援を充実させる目的で児童指導員補助を採用する事業所もみられます。
機能訓練職員・看護職員
機能訓練職員は機能訓練を行う場合、看護職員は医療的ケアを行う場合に配置する職種です。
看護職員については、地域の訪問看護事業所や医療機関の看護職員が事業所に訪問する体制を整備していれば配置を省略できます。
また、機能訓練職員や看護職員を配置した場合は児童指導員または保育士の合計人数としてカウントできますが、過半数を下回る必要があります。
例えば、児童指導員または保育士を合計4人以上配置する必要のある事業所の場合は、合計人数としてカウントできる機能訓練職員や看護職員は2人までです。
児童発達支援と放課後等デイサービスの設備基準
児童発達支援と放課後等デイサービスの設備基準は共通しています。
そのため、多機能型事業所として児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に運営する事業所が多く見られます。
また、2018(平成30)年からは共生型サービス制度が開始され、所定の要件を満たせば児童発達支援や放課後等デイサービスと同時に介護保険の通所介護サービスを提供できるようになりました。
ただし、児童発達支援や放課後等デイサービス事業所を開設する自治体によっては、独自の設備基準を定めている場合があります。
事務所の新築・増改築や賃貸にあたっては、建築基準法や消防法の基準も満たさなくてはなりません。
開業用物件を探す前に、自治体の障害福祉課や建築関係部門、消防署に前もって相談するとよいでしょう。
開業前後のトラブルを未然に防ぎ児童の健全な支援につなげるためには、近隣住民や建物の大家・オーナーなどへの事前説明も大切です。
ここでは、東京都における児童発達支援と放課後等デイサービスの設備基準を紹介します。
▼児童発達支援・放課後等デイサービスの設備基準の例(東京都)
| 設置する部屋 | 要件 |
|---|---|
| 指導訓練室 | ・定員は最低でも10名 ・児童発達支援の場合は児童1人あたり3㎡以上 ・放課後等デイサービスの場合は児童1人あたり4㎡以上 ※国の基準は、児童1人あたりの面積が2.47㎡以上 |
| 事務室 | ・4~5㎡以上が目安 ・扉に鍵を付けるなど、児童が入らないよう配慮する ・固定パーティションで指導訓練室と区切る場合は、安全性・強度・高さにも配慮が必要 |
| 相談室 | ・4~5㎡以上が目安 ・相談内容が外部に漏れないよう配慮する |
| トイレ | ・利用定員に応じた個数を用意する(2ヶ所以上) ・児童の障害の程度に配慮する ・専用のトイレを設置する |
| 手洗い設備 | ・手洗いとうがいをする設備 ・トイレ後の手洗い設備 ・コップ等を洗う設備を別に確保する |
参考:「児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業の基準等について」(東京都福祉保健局)
指導訓練室は広さ・数に注意
国の基準では児童1人あたりの面積が2.47㎡以上ですが、自治体によっては面積や訓練室の数について独自の条件を定めている場合があります。
例えば新潟市では、指導訓練室の広さを児童1人あたり4.12㎡以上を目安としています。
名古屋市の場合だと、定員11人以上の場合は広さ30㎡の指導訓練室に加えて「定員×3㎡-30㎡」の部屋の確保が必要です。
児童発達支援や放課後等デイサービスを開業する際に、利用定員1人あたりの指導訓練室の広さを3㎡以上確保しておくと将来の事業拡大にも有利でしょう。
また、指導訓練室には、訓練に必要な機械器具類を備えておく必要があります。
障害児の安全面への配慮として、指導訓練室に死角ができないレイアウトにしたり、照明設備に飛散防止を取ったりするなどの対応も重要です。
その他の設備・備品
静養室を設置しておくと、児童の気持ちを落ち着かせるスペースとして利用できて便利です。
前述した共生型サービスを提供する際の設備基準にも、静養室の設置について定められています。
送迎サービスを提供する場合は、児童が安全に乗降できる場所や駐車場も確保しておきます。
事業計画にあわせて、児童発達支援や放課後等デイサービスの提供に必要な備品・設備も用意しておきましょう。
児童発達支援と放課後等デイサービスの運営基準
児童発達支援と放課後等デイサービスの運営基準も共通です。
運営基準は厚生労働省通知に沿って、都道府県や政令指定都市・中核市の条例で定められています。
運営基準に定められている主な内容を確認しておきましょう。
▼児童発達支援と放課後等デイサービスの主な運営基準
| 利用定員 | 10名以上 |
|---|---|
| 契約支給量の報告 | 通所受給者証に契約支給量を明記し、自治体に報告 |
| サービス提供拒否の禁止 | 以下のような正当な理由がない限り、事業所はサービス提供を拒めない ・新規に児童を受け入れた結果、利用定員を超過する ・事業所として適切な支援が困難である ・何度も運営規程に違反する |
| 心身の状況把握 | 児童の心身の状況や他のサービスの利用状況などを把握する |
| サービス提供記録の作成 | サービス提供の日時・内容などを記録し、保護者の確認を受ける |
| 利用者負担額の受領 | サービス利用に関する自己負担額を収受する 法定代理受領の手続きも行う |
| 個別支援計画の作成 | 児童発達支援管理責任者が自ら作成する |
| 指導・訓練の実施 | 障害児の心身の状態を把握した上で、適切な技術・知見をもって支援を行う |
| 緊急時の対応 | サービス提供中にケガ・病気が生じた場合などに、医療機関への連絡を行う等必要な対応を行う |
| 勤務体制の確保 | 月ごとにシフト表を作成し、適切な支援を提供できる体制を整えておく 研修実施やハラスメント防止といった労務管理も実施する |
| 衛生管理 | 事業所内の設備や水の衛生管理や食中毒・感染症のまん延予防を実施 |
| 身体拘束等の禁止 | 自傷他害の恐れが高い場合を除き、身体拘束を禁止する |
| 虐待等の禁止 | 児童虐待を禁止すると共に、虐待防止に関する研修等を実施する |
| 秘密保持 | 支援業務で知り得た児童・家族の情報を正当な理由なく漏らすことの禁止 |
| 苦情解決 | 児童や保護者から苦情を受けた際に適切な対応を行う 苦情受付窓口を明確化しておく |
運営基準に基づく運営規程の作成
事業所では運営基準をもとに運営規程を作成し、重要事項説明書と一緒に手渡した上で説明を行い、サービス提供の同意を得る必要があります。
運営規程には次の内容を定めておく必要があります。
- 事業の目的及び運営の方針
- 従業者の職種・人数及び職務内容
- 営業日と営業時間
- 利用定員
- 支援内容と保護者から受領する費用の金額・内訳
- 通常の事業の実施地域
- サービスの利用に当たっての留意事項
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 支援対象の障害の種類を定めた場合は、その障害の種類
- 虐待防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
参考:「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(e-GOV法令検索)
2024(令和6)年からBCP策定も義務化
2024年4月からは、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所でも業務継続計画(BCP)の策定が義務づけられます。
障害児や家族の暮らしに欠かせないサービスであり、障害児の発達や心情安定の観点からも安定かつ継続したサービス提供が事業所の責務です。
備蓄品の確保や業務継続計画に関する研修はもちろん、万が一感染症や災害が発生した時の初動対応や業務再開プロセスについてあらかじめ検討しておきましょう。
なお、厚生労働省では「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を公表しています。
業務継続計画を作成する際には参考にしてください。
児童発達支援と放課後等デイサービスの加算要件
児童発達支援と放課後等デイサービスの報酬加算要件も、ほとんどの部分で共通しています。
ただし、放課後等デイサービスの専門的支援加算については児童指導員と保育士は対象外となるのでご注意ください。
加算できる単位が増えるほど事業所としての支援内容が充実し、経営面でも有利です。
加算される単位数は、事業所の定員や加算項目に対する取組内容などによって変化します。
▼支援の充実度に応じて適用される加算
| 加算項目 | 加算条件 |
|---|---|
| 児童指導員等加配加算 | 人員基準を上回る児童指導員・保育士等を配置 |
| 専門的支援加算 | 所定の人員に加えて理学療法士などの専門職を配置 |
| 看護職員加配加算 | 医療的ケア児の受け入れ体制を整備して看護職員を配置(主に重症心身障害児を受け入れる事業所のみ適用) |
| 家庭連携加算 | 障害児・家族に障害者の居宅で相談援助を実施 |
| 事業所内相談支援加算 | 障害児・家族に事業所内で相談援助を実施 |
| 利用者負担額上限額管理加算 | 利用者負担上限額を管理(最も利用数が多い事業所が加算算定するのが一般的) |
| 福祉専門職員配置等加算 | 社会福祉士・介護福祉士などの雇用率に応じて加算 |
| 欠席時対応加算 | 利用予定の障害児が欠席した際に連絡調整・相談援助を実施 |
| 特別支援加算 | 専門職により計画的に機能訓練を実施 |
| 強度行動障害児支援加算 | 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者が、強度行動障害のある子どもを支援 |
| 個別サポート加算 | ケアニーズの高い障害児や要保護・要支援児童を支援 |
| 医療連携体制加算 | 医療機関と連携して看護職員が事業所を訪問し、障害児に看護を実施 |
| 送迎加算 | 居宅等と事業所間を送迎した場合に加算 |
| 延長支援加算 | 運営規程に定める営業時間の前後に支援を実施した場合に加算 |
| 関係機関連携加算 | 保育所・学校と連携して個別支援計画を作成、または就学先・就職先と連絡調整を実施 |
| 保育・教育等移行支援加算 | 支援の結果、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所を退所できた時 |
福祉・介護職員処遇改善加算制度
従業員の賃上げを目的とした加算として、福祉・介護職員処遇改善加算制度が設けられています。
事業所が得た給付費や各種加算の合計単位に、所定の加算率がプラスされます。
福祉・介護職員処遇改善加算で得た資金はすべて職員の給与・賞与に反映させるルールで、全職員への周知も必須です。
加算を算定するには、最低でもキャリアパス要件(Ⅰ)または(Ⅱ)を満たす必要があります。
加算の種類によっては、キャリアパス要件(Ⅲ)や職場環境等要件も求められます。
▼福祉・介護職員処遇改善加算の要件
| キャリアパス要件(Ⅰ) | 職務内容や責任に応じた賃金体系・任用基準を整備 |
| キャリアパス要件(Ⅱ) | 支援技術の向上計画を立てた上で研修を実施、または研修の機会を設定 |
| キャリアパス要件(Ⅲ) | 評価制度に基づく昇給制度または定期昇給制度の実施 |
| 職場環境等要件 | 職場環境の改善を実施 |
参考:「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(厚生労働省)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算制度
職場環境の改善に積極的に取り組み、ホームページ等で事業所内外に見える化している事業所は、福祉・介護職員処遇改善加算に加えて福祉・介護職員等特定処遇改善加算も算定できます。
福祉職員等特定処遇改善加算については事務職員などにも配分可能です。
さらに、職員のベースアップ目的で加算できる福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算制度も設けられています。
児童発達支援と放課後等デイサービスの減算要件
児童発達支援と放課後等デイサービスには、減算ルールも設けられています。
所定単位数の15~50%が減算されるため、事業所運営に大きな影響を与えます。
減算が続くと自治体に不適切な運営状況だと判断され、実地指導・監査の対象になる可能性もあります。
なお、急な欠勤などやむを得ない事情で必要人数を満たせない場合でも、その日のサービスを停止する必要はありません。
職員の退職や育児・介護休業などで欠員が長期化し、人員を補充できなかった場合は後述するサービス提供職員欠如減算の対象になる可能性があります。
▼児童発達支援や放課後等デイサービスの減算項目・要件
| 減算項目 | 減算となる範囲 | 減算要件 |
|---|---|---|
| 定員超過利用減算 | 利用者全員分 | 1日の利用者数または3ヶ月平均の利用者数が定員を上回った場合 |
| サービス提供職員欠如減算 | 利用者全員分 | 人員配置が基準を下回った場合 |
| 児童発達支援管理責任者欠如減算 | 利用者全員分 | 児童発達支援管理責任者を配置せずに事業所を運営した場合 |
| 個別支援計画未作成減算 | 未作成の児童分 | 個別支援計画を作成しないまま支援を実施した場合 |
| 自己評価結果等未公表減算 | 利用者全員分 | 事業所の自己評価結果等を公表していない場合 |
| 開所時間減算 | 利用者全員分 | 運営規程に定めた営業時間が6時間未満の場合 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 利用者全員分 | 身体拘束等の適正化を図る措置を講じていない場合 |
児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所を開業するには
ここまで紹介したとおり、児童発達支援と放課後等デイサービスはサービスの対象年齢は異なるものの、運営基準や必要な人員配置など共通する部分も多くあります。
そのため、多機能型事業所として児童発達支援と放課後等デイサービスを経営する事業者が数多くみられます。
多機能型事業所とは、児童福祉法に基づく複数の事業を一体的に行える事業所です。
障害福祉サービスの一部サービスも多機能型事業所として運営でき、例えば放課後等デイサービス事業所と就労継続支援B型事業所・生活介護事業所の3事業を1つの建物内で運営することも可能です。
ただし、事業ごとの指定基準を満たす必要があります。
▼多機能型として運営可能な事業
| 児童福祉法に基づくサービス | ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・居宅訪問型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援 |
| 障害福祉サービス | ・生活介護 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 |
さらに、2018年度からは介護保険の通所介護サービス(高齢者向けのデイサービス)も共生型サービスとして一体的に運用できる仕組みが整備されました。
多機能型・共生型とも人員配置基準や設備基準に特例が設けられており、児童発達支援と放課後等デイサービスを単体で運営するよりも収益性が高まるメリットがあります。
ミライクスの放課後等デイサービス実践講座なら、専門家による研修を通じて放課後等デイサービス・児童発達支援事業所を経営するノウハウを効率的に学べます。
約6ヶ月間の合同研修で、経営者同士の横のつながりができるのも魅力です。
研修修了後すぐに放課後等デイサービス事業所を開業できるように、物件確保や人材採用のサポートも行っています。
放課後等デイサービスを開業しようとお考えの方は、ぜひ無料セミナーをご予約ください。
「新版 障害児通所支援ハンドブック」(一般社団法人全国児童発達支援協議会)
「障害者総合支援法事業者ハンドブック 指定基準編 2022年版-人員・設備・運営基準とその解釈」(中央法規出版)
「障害者総合支援法事業者ハンドブック 報酬編 2022年版-報酬告示と留意事項通知」(中央法規出版)
「障害児支援施策」(厚生労働省) 「児童福祉法」(e-GOV法令検索) 「1歳6か月児健診からの発達が気になる子の早期支援」(静岡市) 『「介護給付費等の支給決定等について」の一部改正について(令和4年4月1日 厚生労働省一部改正通知)』(新潟県) 「放課後等デイサービスの対象範囲の拡大について」(厚生労働省) 「居宅訪問型児童発達支援」(北海道恵庭市) 「常勤・非常勤及び常勤換算方法について」(千葉県柏市) 「2、常勤・非常勤・専従・兼務に関する考え方<共通>」(福岡県福岡市) 「管理者(施設長)の資格要件及び兼務関係」(北海道札幌市) 「障害児通所支援事業等指定申請の手引」(和歌山県) 「障害福祉現場の人材確保・業務効率化について」(厚生労働省) 「児童指導員」(大阪府) 「障害児通所支援に係る指定基準等の見直しについて」(愛媛県) 「障害児通所支援事業所等(障害児通所支援、生活介護およびグループホーム)における安全な医療的ケアの実施体制のための手引き」(障害児通所支援事業所等における安全な医療的ケアの実施体制の構築に関する調査研究 検討委員会) 「共生型サービス」(厚生労働省) 「共生型サービスについて(障害福祉サービス等を始めたい介護サービス事業者向け)」(北海道札幌市) 「児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業者指定申請の手引き」(新潟県新潟市) 「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)」(厚生労働省) 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(厚生労働省) 「多機能型事業所について」(大阪府)