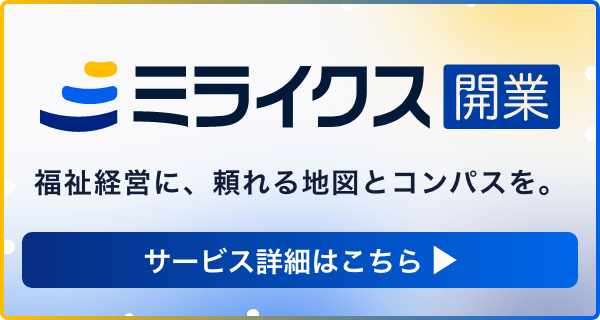事業を探す
2023.6.4
2023.5.29
児童発達支援管理責任者とは?資格要件から仕事内容まで解説!

そのため、児発管の資格取得には実務経験と所定の研修修了が必要とされています。
この記事では、児発管の役割、資格取得の要件、および具体的な仕事内容について解説します。
目次
児童発達支援管理責任者とは?
児童発達支援管理責任者(略称:児発管)とは、個別支援計画の作成など、障害児サービスの中核的業務を担う職種です。
ここでは、児童発達支援管理責任者を目指す方に向け、児発管の役割や勤務先、児発管になる方法などについて解説します。
児童発達支援管理責任者の役割
児童発達支援管理責任者の役割は以下の2つに分けられます。
- サービス提供の流れの管理
- サービス提供に当たる職員への指導
▼児発管の役割と内容
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 1.サービス提供の流れの管理 | 児童が抱える課題の把握(アセスメント) ↓ 個別支援計画の作成 ↓ 計画実施状況の把握(モニタリング) ↓ 計画の評価と見直し |
| サービス提供に当たる職員への指導 | 個別支援計画作成者の立場から、計画に沿ったサービスが提供されるよう職員を指導する |
参考:「障害児支援(通所・入所共通) に係る報酬・基準について ≪論点等≫」(厚生労働省)
児童発達支援管理責任者の主な勤務先
児童発達支援管理責任者の勤務先を多い順に示すと、次のとおりです。
- 放課後等デイサービス事業所
- 児童発達支援事業所
- 保育所等訪問支援事業所
- 居宅訪問型児童発達支援事業所
▼児発管の主な勤務先
| 勤務先 | 事業の内容 |
|---|---|
| 放課後等デイサービス事業所 | 小学校就学後の児童や生徒が通って、日常生活動作などを身に付ける(児童福祉法 6条の2の2 第4項) |
| 児童発達支援事業所 | 小学校就学前の児童が通って、日常生活動作などを身に付ける(同条2項) |
| 保育所等訪問支援事業所 | 児童が通う保育所などを訪問して、健常児と仲良く過ごせるよう支援する(同条6項) |
| 居宅訪問型児童発達支援事業所 | 通所困難な児童の居宅を訪問して、日常生活動作などを身に付けさせる(同条5項) |
参考:「障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の状況」(厚生労働省)
児童発達支援管理責任者になるには?

児童発達支援管理責任者になるには、厚労省告示に従い資格要件を満たさなければなりません。
資格取得後も、5年ごとに更新研修修了による資格更新が必要です。
ここでは、児発管の資格取得までの流れ(1~5)と取得後5年ごとの更新研修(6)について解説します。
▼児童発達支援管理責任者になるまでの流れ
- 実務経験を積む
- 基礎研修を修了する
- OJTを受ける
- 実践研修を修了する
- 児発管の資格を取得する
- 更新研修を修了する
1.実務経験を積む
実務経験には次の3パターンあり、そのいずれかに該当する必要があります。
(1)相談支援または直接支援に合計5年以上従事した経験がある人
相談支援または直接支援に従事した期間が合計5年以上で、そのうち障害者・障害児を対象とする期間が3年以上ある人が該当します。
相談支援、直接支援とはそれぞれ以下の業務を指します。
▼相談支援と直接支援の意味
| 相談支援 | 日常生活の自立に関する相談に応じ、助言・指導を行う |
|---|---|
| 直接支援 |
|
実務要件を満たしているかどうかは以下の計算式で確認できます。
ア+イ(5年以上)−(ウ+エ)≧ 3年
ア…相談支援に従事した期間
- 障害児相談支援事業など
- 児童相談所など
- 障害児入所施設など
- 障害者職業センターなど
- 大学以外の学校
- 病院または診療所※
※社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修以上の研修を修了した人、国家資格を有する人のうち、アの対象事業・施設(病院または診療所を除く)で相談支援業務に1年以上従事した人のみ
イ…直接支援に従事した期間
- 社会福祉主事任用資格者
- 介護職員初任者研修以上の研修を修了した人(介護福祉士を含む)
- 保育士
- 児童指導員任用資格者
- 精神障害者社会復帰指導員任用資格者
- 障害児入所施設など
- 障害児通所支援事業など
- 病院・診療所・薬局など
- 学校(大学を除く)
- 障害者の雇用促進のための会社(特例子会社)など
ウ…老人福祉施設などで相談支援に従事した期間
- 老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 救護施設
- 更生施設
- 地域包括支援センター
エ…イの対象者が老人福祉施設などで直接支援に従事した期間
- 老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 病院または診療所の療養病床関係病室
- 老人居宅介護事業
- 特例子会社
- 助成金受給事業所
ア+イ(合計5年以上)からウ+エを引いた年数が3年以上であれば、実務経験要件を満たしていると考えられます。
(2)直接支援に8年以上従事した経験がある人
社会福祉主事任用資格等を保有していない場合は、直接支援に従事する期間が8年以上、そのうち障害者や障害児などを対象とする期間が3年以上必要です。
要件を満たしているかどうかは以下の計算式で確認できます。
ア(8年以上)− イ ≧ 3年
ア…直接支援に従事した期間
- 障害児入所施設など
- 障害児通所支援事業など
- 病院・診療所・薬局など
- 学校(大学を除く)
- 障害者の雇用促進のための会社(特例子会社)など
イ…老人福祉施設などで直接支援に従事した期間
- 老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 病院または診療所の療養病床関係病室
- 老人居宅介護事業
- 特例子会社
- 助成金受給事業所
ア(8年以上)からイを引いた年数が3年以上であれば、実務経験要件を満たしているでしょう。
(3)指定の国家資格等が必要な業務に5年以上従事した経験がある人
指定の国家資格等が必要な業務に5年以上従事し、そのうち障害者・障害児などの相談支援または直接支援に合計3年以上従事する人が該当します。
国家資格による業務に従事する期間と、相談支援・直接支援に従事する期間は重複しても問題ありません。
実務要件を満たしているかどうかは以下の2つの計算式で確認できます。
a ア≧5年
b (イ+ウ)−(エ+オ)≧ 3年
ア…指定の国家資格等が必要な業務に従事した期間
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、技師装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
イ…相談支援に従事した期間
- 障害児相談支援事業など
- 児童相談所など
- 障害児入所施設など
- 障害者職業センターなど
- 大学以外の学校
- 病院または診療所※
※社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修以上の研修を修了した人、国家資格を有する人のうち、アの対象事業・施設(病院または診療所を除く)で相談支援業務に1年以上従事した人のみ
ウ…直接支援業務に従事した期間
- 障害児入所施設など
- 障害児通所支援事業など
- 病院・診療所・薬局など
- 学校(大学を除く)
- 障害者の雇用促進のための会社(特例子会社)など
エ…老人福祉施設などで相談支援に従事した期間
- 老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 救護施設
- 更正施設
- 介護医療院
- 地域包括支援センター
オ…老人福祉施設などで直接支援に従事した期間
- 老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 病院または診療所の療養病床関係病室
- 老人居宅介護事業
- 特例子会社
- 助成金受給事業所
国家資格等が必要な業務に5年以上従事し、イとウの合計からエとオを引いた年数が3年以上であれば実務経験要件を満たしています。
2. 基礎研修を修了する
実務経験要件を満たす2年前になれば、基礎研修を受講できます。
基礎研修は次の2つから成り、両方の修了により基礎研修修了者となります。
- 児童発達支援管理責任者基礎研修
- 相談支援従事者初任者研修(講義部分)
修了者には修了証明書が交付されます。
児童発達支援管理責任者基礎研修
児童発達支援管理責任者基礎研修は基礎研修の中心的研修であり、次のいずれかに該当する人が受講できます。
- 実務経験を満たす人
- 今後2年以内に実務経験を満たす見込みの人
研修内容は次のとおりです。
▼児童発達支援管理責任者基礎研修の内容
| 区分 | 科目 | 時間数 |
|---|---|---|
| 講義 | 児童発達支援管理責任者の基本姿勢とサービス提供のプロセスに関する講義 | 7.5時間 |
| 演習 | サービス提供プロセスの管理に関する演習 | 7.5時間 |
| 合計 | 15時間 | |
参考:「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」(厚生労働省告示第二百三十号)
修了者には修了証明書が交付されます。
相談支援従事者初任者研修
相談支援従事者初任者研修とは、相談支援の基本を習得する研修です。
相談支援は児発管に欠かせない仕事ですが、児童発達支援管理責任者基礎研修では触れられないため、この研修で補足することになっています(そのため「補足研修」とも呼ばれます)。
児童発達支援管理責任者基礎演習では、相談支援従事者初任者研修のうち講義部分を受講します。
講義の内容は以下のとおりです。
▼相談支援従事者初任者研修(講義部分)の内容
| 区分 | 科目 | 時間数 |
|---|---|---|
| 講義 | 障害児者の地域支援と相談支援従事者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)の役割に関する講義 | 5時間 |
| 相談支援におけるケアマネジメントの手法に関する講義 | 3時間 | |
| 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律および児童福祉法の概要ならびにサービス提供のプロセスに関する講義 | 3時間 | |
| 合計 | 11時間 | |
参考:「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」(厚生労働省告示第二百三十号)
3. OJTを受ける
基礎研修修了後は、相談支援または直接支援の業務に従事するOJT期間となります。
既に児童発達支援管理責任者が1名配置されている事業所であれば2人目の児発管として配置でき、児童のアセスメントと個別支援計画の原案の作成ができます。
OJT(On the Job Training)とは、職場での実践を通じて仕事の知識や技術を身に付ける訓練のことです。
OJTは、実践的な人材育成手段として、介護に限らず多くの職場で取り入れられています。
児発管の資格取得のためのOJTの要件は、基礎研修修了後から実践研修受講までの5年間に通算2年以上相談支援または直接支援の業務に従事することです。
4. 実践研修を修了する
OJTを終えた人は児童発達支援管理責任者実践研修を受講できます。
実践研修の内容は次のとおりです。
▼児童発達支援管理責任者実践研修の内容
| 区分 | 科目 | 時間数 |
|---|---|---|
| 講義 | 障害福祉の動向に関する講義 | 1時間 |
| 講義・演習 | サービス提供に関する講義および演習 | 6.5時間 |
| 人材育成の手法に関する講義および演習 | 3.5時間 | |
| 多職種および地域連携に関する講義および演習 | 3.5時間 | |
| 合計 | 14.5時間 | |
参考:「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」(厚生労働省告示第二百三十号)
修了者には修了証明書が交付され、実践研修修了者となります。
5. 児発管の資格を取得する
実践研修修了者となった時点で児童発達支援管理責任者の資格を取得したことになります。
なお、制度改正に伴う経過措置として、以下の「みなし配置」が認められています。
2018(平成30)年度までに旧体系での研修を受講済みの人
令和5年度末(2024年3月末)までは、児童発達支援管理責任者更新研修の修了前でも児童発達支援管理責任者として引き続き業務を行えます。
ただし、令和5年度末までに更新研修を受講しなくてはなりません。
令和元年度から令和3年度に基礎研修を修了し、実務要件を満たしている人
2019年4月1日から2022年3月31日までの間に基礎研修を修了し、児発管として配置されるために必要な実務経験の要件を満たしている人は、基礎研修修了から3年間に限り児童発達支援管理責任者として配置できます。
みなし児発管の期間経過後も児発管として働くには、みなし期間内に実践研修を修了して正式に児発管とならなければなりません。
6. 更新研修を修了する
実践研修の修了日(児発管の資格取得日)の翌年を1年目として5年目の末日までに、児童発達支援管理責任者更新研修を修了しなければなりません。
次いで、更新研修修了の翌年を1年目として5年目の末日までに2回目の更新研修を修了することが必要です。
その後も5年ごとに更新研修を修了する必要があります。
更新研修の内容は次のとおりです。
▼児童発達支援管理責任者更新研修の内容
| 区分 | 科目 | 時間数 |
|---|---|---|
| 講義 | 障害福祉の動向に関する講義 | 1時間 |
| 講義・演習 | サービス提供の自己検証に関する演習 | 5時間 |
| サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義および演習 | 7時間 | |
| 合計 | 13時間 | |
参考:「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」(厚生労働省告示第二百三十号)
修了者には修了証明書が交付され、更新研修修了者となります。
期日までに更新研修を修了しないと、児童発達支援管理責任者実践研修の修了証書が失効し、児発管として働くことができなくなります。
その場合も、改めて実践研修を修了すれば、児発管として働くことが可能です。
児童発達支援管理責任者の平均年収は?
児童発達支援管理責任者の平均年収は、児童発達支援で449万円程度、放課後等デイサービスで394万円程度と考えられます。
厚生労働省のデータによると、令和3年9月現在、児童発達支援と放課後等デイサービスの職員の平均月給額は次のようになっています。
▼処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額
| 役職/施設 | 管理職 | 管理職以外 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 37万4,060円 | 27万7,030円 |
| 放課後等デイサービス | 32万8,480円 | 26万7,430円 |
※令和3年度に福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)の届出をしている施設・事業所において、令和2年9月と令和3年9月ともに在籍している常勤の福祉・介護職員が対象。
※平均給与額は、基本給+手当+一時金(賞与・その他の臨時支給分。4~9月支給金額の1/6)により算出。また、10円未満を四捨五入している。
出典:「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(厚生労働省)
児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成などサービス提供の流れを管理し、サービス提供に当たる職員への指導も行う、管理職に当たる職種です。
管理職である児発管の月給が管理職以外の職員より高いのは、次の2つの理由によるものと考えられます。
- 児発管は、障害児サービスの中核的職種として、重要かつ大量の仕事をこなさなければならないこと
- 児発管は、要職の実務経験を経たうえで高度な内容の研修を修了してはじめて取得できるグレードの高い資格であること
児童発達支援管理責任者の仕事はキツい?

児発管は障害児サービスの中核的役職で給料も高めですが、その分、実際の仕事はキツいのでしょうか。
結論から言えば、児発管の仕事は決して楽とはいえないでしょう。
それを示すのが、次の3つです。
- 具体的な仕事内容
- 1日のスケジュール
- 管理者兼務や他サービスの児発管兼務があること
それぞれについて見ていきます。
児童発達支援管理責任者の仕事内容
児童発達支援管理責任者の仕事内容については「児童発達支援管理責任者の役割」で触れましたが、もう少し詳しく仕事の目的と内容について見てみましょう。
アセスメント
| 目的 | 個々の児童にふさわしい個別支援計画の基礎とするため |
|---|---|
| 内容 |
児童が抱える課題の把握
|
個別支援計画の作成
| 目的 | 職員の意識を統一し、足並みのそろった支援をするため |
|---|---|
| 内容 |
課題をふまえて児童に提供する支援の中身
|
モニタリング
| 目的 | 計画がどのように実施されているかを把握し、計画の評価につなげるため |
|---|---|
| 内容 |
計画実施状況の把握
|
評価と見直し
| 目的 | 個別支援計画を個々の児童にふさわしいものに近づけるため |
|---|---|
| 内容 |
個別支援計画の評価
個別支援計画の見直し
|
職員指導
| 目的 | 個別支援計画作成者の立場から、計画の真意を現場職員に伝え、計画を実現できるようにするため |
|---|---|
| 内容 | 計画に沿ったサービス提供がなされるよう現場の職員を指導する |
児童発達支援管理責任者の1日の流れ
児発管の1日の仕事の流れについて、放課後等デイサービスでの一例を紹介します。
▼児発管の1日の流れ(イメージ)
| 9:00~9:30 |
<朝礼>
|
|---|---|
| 9:30~10:00 | 児童の迎えをフォロー |
| 10:00~11:00 |
|
| 11:00~12:00 |
|
| 12:00~13:00 |
<昼休憩>
|
| 13:00~14:00 |
|
| 14:00~15:00 |
|
| 15:00~16:00 |
|
| 16:00~17:30 | 児童の送りをフォロー |
| 17:30~17:45 | 掃除 |
| 17:45~18:00 | 1日の振り返り・反省会 |
| 18:00 | 退勤 |
アセスメント・個別支援計画の作成・モニタリング・評価と見直しを行うには、子どもの思いや状態を直に感じ取ることが欠かせません。
児発管が送迎・昼食・おやつなど現場の仕事にも携わるのは、こうした理由によるものです。
事業所によって多少の違いはありますが、児発管の1日の仕事はとても忙しいといえるでしょう。
児童発達支援管理責任者が兼務できる仕事
児発管が兼務できる他職種は、次のとおりです。
▼放課後等デイサービスのみの事業所の場合
| 他の職種 | 兼務の可否 |
|---|---|
| 施設の管理者 | 〇 |
| 児童指導員 |
× 児発管の業務に支障がない範囲で、児童指導員や保育士の業務をサポートすることはできる |
| 保育士 |
▼多機能型事業所(児童発達支援と放課後等デイサービを同じ場所で行う事業所)の場合
| 他の職種 | 兼務の可否 |
|---|---|
| 施設の管理者 | 〇 |
| 各サービスの児発管 | 〇 |
| 児童指導員 |
× 児発管の業務に支障がない範囲で、児童指導員や保育士の業務をサポートすることはできる |
| 保育士 |
参考:「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」(厚生労働省)
児発管の仕事に加え、次のような管理者の仕事を兼務すれば、さらに忙しくなることは明らかです。
- 施設全体のとりまとめ
- 施設の設備や備品の管理
- スタッフの任免手続
- スタッフへの助言指導
また、多機能型事業所で児童発達支援と放課後等デイサービス双方の児発管を兼務すれば、単独型事業所以上に負担が大きくなるでしょう。
児発管を目指すのなら、こうした多忙な職種であることも心しておきましょう。
2024年の法改正で児童発達支援管理責任者の仕事はどう変わる?
改正児童福祉法が2024年4月1日より施行されれば、児童発達支援センターの福祉型と医療型の区分けがなくなります。
児童が「障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにする」ためというのが国の説明です(※)。
福祉型児童発達支援センターに勤務する児童発達支援管理責任者は、これまで医療型の対象であった肢体不自由児も担当するようになります。
医療やリハビリテーションの知識がないと肢体不自由児の個別支援計画の作成が難しくなるなど、児発管のスキルアップが求められる時代になるといえるでしょう。
児発管を採用する側もこれまで以上に厳しい目で応募者を審査し、新たな制度に対応できる人材を確保しなければなりません。
ミライクスでは、障害者福祉事業の開業をサポートしています。
障害児通所支援を開業したい方には、児発管の採用と育成についてのレクチャーも行われる「放課後等デイサービス実践講座」がおすすめです。
開業後に必要となるアセスメントや個別支援計画などのひな形も充実しております。
まずは無料セミナーでお気軽にご相談ください。
※参考:「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の概要」(厚生労働省)